自己学習サイトのヘッダー
ITリーダーやITマネージャーのための"ゆる〜い"学びの研究室
交響曲の研究2
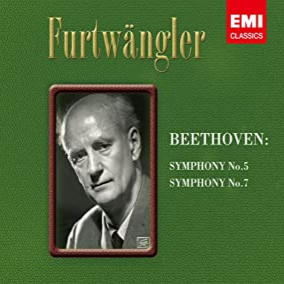 |
| 作品 | ベートーベン 交響曲第9番 | ||
| 鑑賞 日 |
201X年12月8日 | ||
| 鑑賞 記録 |
とても風が強く寒い日であった。北日本では雪混じりの嵐。12月も8日を経過し、師走の町はどこかせわしない。 自分にとってアクトシティー大ホールは初めて。なぜか地下の入場口から階段で1Fに登る構造になっており、ドアをくぐると中ホールのこじんまりした雰囲気とはうって変わって、巨大なホールが現れた。ステージ対面だけでなく左右に4階もの客席があり、その概容に圧倒される。試しに3階に行って見ると、ステージを真上から見下ろす感じで、高さに少々驚いた。 座席はS指定席、18列目の15番。ステージをやや左方向から見る感じで、近すぎず、遠過ぎず、まあまあの席。もっと近くで見たいとは思ったが、これだけ巨大なホールを考えると充分良い席であろう。左は家族4人で、わいわいがやがやで楽しそう。小学校中学年程度のお子さんが居たが、1時間以上の演奏に退屈しないのだろうか?と他人事ではあるが心配してしまった。右は中老の1人が開演直前に座る。あまり親近感は無い人。全体的にはぎっしり埋まってほぼ満席であったので、近くに座る人がどんな人かは結構重要。 開演は19:00とあったが、少し遅れているようで、19:05位からオーケストラのメンバーが現れ始めた。楽器の配置は、ステージの左に重点音楽器、バイオリンは左右に分かれている。打楽器は右。この配置は初めて経験するもの。合唱団はこの段階ではまだ入場しないようだ。 指揮者の高関健さんは、案外小柄で、しかし動きは非常に俊敏、とても1955年生まれ(58才)には見えない。簡単なお辞儀をして、おもむろに演奏が開始される。 第一楽章。 一言で言うと「こんなすごい曲だったんだ!」。25年前、会社の上司に無理やり連れてこられた第九。確か2回は行っているはず。その時には全く感動も何も無かった。が、それから25年。この楽章の緻密な構造とその発想のすばらしさに、本当に感動した。厳かな雰囲気の最初のテーマから、ドラマチックに、ダイナミックに曲が動いていく。どんどん引き込まれていき、あっと言う間に終わってしまった。 第二楽章 軽快なテンポで最後まで一気に行った感じ。ティンパニーの音が印象的。この楽章の所々止まるような感じの箇所が、とてもよいタイミングで、おどけた曲のイメージに合っていたと思う。この楽章はやはりスケルフォ楽章なのだ。この楽章が終わると、合唱団の入場。何と150人以上は居るだろう。浜松フロイデ合唱団。アマチュアなのだと思うが、パンフを見ると毎年この第九の合唱を担当しており、今年で31年目だそうだ。継続は本当にすごいことだ。 第三楽章 テンポはかなり速め。しかし、その速さがこの楽章の旋律を浮かび上がらせる。ショルティのCDではこの楽章に20分以上の時間を費やしていて、音の洪水がじわりじわり攻めてくる感じしか無かった。今日はそれとは全く違った曲に聴こえた。こんなにきれいな旋律が組み込まれていたなんて! 途中の盛り上がり箇所も非常にさっぱりした感じで「ブレイク」といった感じ。第三楽章はこのくらいのテンポでコンパクトにやった方が生きると思う。時間にすると15分も無かったように思う。 第四楽章 ちょっとテンポが速いかな、と感じているうちに歓喜の主題に入る。途中の大太鼓は明らかに「走って」いたように感じた。2回目の歓喜の合唱の前、跳ねるような演奏から、小さな音に変化し、一気に盛り上がるところがこの楽章の聴き所であると思うのだが、ちょっと淡白な感じになっていた。もう少しゆったりさせて、ためて、ぅーーーわあっつて行って欲しかったなあ、惜しいかった。独唱者はバスの男声から入る、よく響く声。さらにテノール、アルト、ソプラノと絡んでいく段は、とてもスリリングで人間の声とは思えない響きだが、楽器からは決して出ない響きでもある。また、合唱団はさすがにすごい迫力。これなら4階席でも充分迫力を届けられる。 また、次の機会にはまた違う第9交響曲を発見することを楽しみにして、家路についた。 |
