上條信一氏がご逝去されました。 これより、雑記帳はブログに移したいと思います。
かつのブログ
全体主義(ファシズム)が復活しつつあるようです。アメリカの一部の州で移民と見られるというだけで逮捕できる等というとんでもない法律が成立していますが、これは日本での話です。
まず、同じ全体主義でもナチスの国家社会主義(ファシズム)と、日本でのかつての軍国主義とは、やったことは似ていますが、最初の発想は全く異なるものです。ナチスのそれは、むしろ困窮する市民によって選挙で選ばれた社会主義的なものだったからです。復活しつつある、というのはこのナチス流のファシズムです。
ナチス即ち国家社会主義ドイツ労働者党が台頭したとき、ドイツの経済状況は疲弊し、労働者は困窮していました。ナチスは貧困の根本原因を、ユダヤ人資本家になすりつけました。
ナチス政治思想は、議会制民主主義を否定し、「指導者原理」という概念により、指導者に対する忠誠と服従を求めました。
宣伝省を設け、情報統制と報道管制を敷きました。
総統であったヒトラーは、群集心理に長け、民衆の人気がありました。
優生学を人種政策に取り入れ、アーリア人種を最も優秀と位置づけました。
今、日本にも良く似た状況の地域があります。
不況で大企業の工場が無くなり、平均所得が300万円以下で、小泉改革によって税収が落ち込み、農業や漁業も難しい状況で、改革を訴える新市長が当選しました。
ヒトラーが、失業者や中小零細業者の不満を上手く利用したのとよく似ています。
ブログを使って、困窮する人たちの心を捉える手法は、群集心理に長けたヒトラーが、今、生きていれば使っているに違いありません。
議会を否定し、自分の不信任に対して議会を解散しています。これもヒトラーと同じです。
自分に絶対服従を要求し、それをしない役所の人を懲戒解雇とし、裁判所の命令も無視しています。これは、まさにヒトラーの言う「指導者原理」そのものです。
議会の否定、裁判の否定、これは三権分立という日本の議会制民主主義の大前提の否定です。つまり間違いなく、声高に全体主義を唱え、民主主義を否定しています。これもヒトラーと同じです。
新聞を偏向報道として議会への取材を拒否しています。反抗する見方への情報統制です。ヒトラーと同じやり方です。
優生学と言うのは、実は日本でもつい最近までありました。ハンセン氏病については既に述べたとおりです。
自身のブログに「高度医療のおかげで機能障害を持ったのを生き残らせている」と記述し、障害者団体やハンセン氏病の団体の怒りを買っていますが、謝罪には応じていません。ヒトラーも優生学を重用しました。これまでの議論で解る様に、ヒトラーと阿久根市長は極めて良く似ています。
良いとか悪いとかでは無く、同じ事をやっていると言うことです。言うまでも無いことですが、民主主義の根幹は選挙による多数決ではありません。諸個人の意思の集合をもって物事を決めるためには、個人の尊重が必要です。
社会全体のために個人が大きな制約を受けるのもやむなしとする、上の様な思想こそが民主主義と対立する概念であり、それを全体主義と呼ぶのです。注;優生学は、遺伝形質に規定された不平等を前提としており、人間というものを、「人の尊厳」においてではなく「価値の優劣」でもって捉えます。だからこそ異人種間の価値的優劣を主張するヒトラーが、優生学を国家的な思想としたのです。
尚、優生学は科学的な意味においても、すでに否定されている疑似科学です。より優秀なものだけが生き残る事に意味はありません。優秀とするのは主観に過ぎません。多様性こそが生命の価値です。
例えば、ニュートンやアインシュタインは、学習障害があったことが知られています。或いはIQが180の人からみれば、あの市長こそが知的障害者であり、彼自身の価値観にって抹殺されるべき存在となってしまいます。私は、民主主義を否定する市長を告発することに興味があるのではないです。何度も書いていますが、あの種の下らない人間を相手にするのは無駄というものです。ヒトラーを説得できる人なぞ居ませんからね。
私が言いたいのは、多くの阿久根市民が、紛れも無い「全体主義者」を市長に選んだ、という震撼すべき事実です。また支持する市議会議員がいる、即ち民主主義に否定的な市議会議員が多くいる、という恐るべき事実です。まさか馬鹿では無いのでしょうから、これは民主主義というものを、未だ理解していない議員が多くいるのだ、ということなのでしょう。
大袈裟ではなく、これは日本の民主主義の危機です。全体主義の脅威はかなり近くまで来ているのかも知れません。実際に、現在の地方経済はかつてのドイツと良く似ています。歴史を学べば、状況がそうさせた、では許されないでしょう。
全体主義(或いは軍国主義)というのは個人主義の反意語である、という当然のことが認識できない人が多くいるのは日本の義務教育の失敗なのかも知れません。
ごく普通の人がどうものを考えるのか、という事で最近ショッキングなことがありました。
その人は星占いは嘘だが血液型性格診断は信じるとか言うので、そんなもの大差無い、事実それは関係ないと言う事は既に証明されているし、信頼できる論文もある、という話をしました。
日本で良く信じられるのはバーナム効果が主な原因という話もしました。すると、驚く無かれ「そんなもの関係ない、事実そうなのだ」との回答。
正直、呆れて言葉が出ませんでした。事実を明らかにするために調査し、論文になり、それが公に認められている、というのが「実験事実」なのですが、この人は「自分がどう感じるのか」を「事実」だと信じているのです。
特にこの人が頭が悪いという訳ではありません。むしろ、普通に言えば良い方に属するでしょう。
ある種の社会的洗脳もあるのでしょうが、もっと大きな問題は、いつも私の言っている「科学する心」を持っていない、ただそれだけのこと。
この方を見て、いわゆる相間とか言われる人達が何故あそこまで頑迷なのかが分かった気がしました。その人の考える事実が「実験事実」ではなく「自分」にあるからでしょう。これはある種の信仰です。事のついでに書いておきますが、いわゆるABO血液型とは赤血球の抗原なのですが、脳には血液脳関門というものがあり、ABO抗原はここを通過できませんので、脳にABO抗原はありません。つまり抗原の型で性格が変わる人は脳でものを考えない人ってことですかね(笑)
正直言って、最近の小中学校の先生の“科学する心”の無さには怒りを通り越して呆れるものがあります。
例えば、これですが、ゲーム脳なんて似非科学を無批判に信じてらっしゃるようです。これは知識の問題では断じてありません。
自然科学の方法論を理解しているなら、ゲーム脳なんて血液型性格診断と同レベルの与太話(参考リンク)だと理解できると思うからです。(参考リンク)いや、信じる信じないは、個人の問題ですからこれ以上言いませんが、実際にこんな与太話を、子供に教えているかと思うと、背筋が凍ります。
ゲームをするかどうか、ではありません。科学する心を完全に放棄して、与太話だろうが何だろうが、考えるよりも信じるような子供を積極的に育てていると言う事実に、です。もし、子供がゲームで遊ぶことに対して何かしらの負い目があれば、無批判に受け入れてしまうでしょう。
更に、最近では、道徳の授業で水にありがとうと言うと結晶が綺麗になるなんて法螺まで教えているそうです。(この元ネタは、単に波動がどうしたとか言う占いみたいな、怪しい儲け話です)子供さんがこんな与太話を吹き込まれたなら、そういう教育は積極的に糾弾すべきと思います。
この駄文をお読みの方々も、教育の荒廃を無視すべきでは無いと思うでしょう?ググってみると、明治時代には野球脳というのが存在したそうです(笑)。
ビートルズ来日の折り、ビートルズの音楽性を批判した自称文化人が居ましたが、その後十年を待たずして、高校の音楽の教科書にはビートルズの曲が載りました。
本質的には、新しいものを敵視し、古い者を良しとする、昔から見られる愚かさがあります。ニセ科学シンポジュウムが開催されました。
昨今、テレビで ABO式の血液型と性格を結びつけた番組の流行と、それに伴う差別が社会問題になっているようで、一々テロップが出たりする様です。
私の考えとしては、非科学的な度合いと差別意識について言えば、この下に書いた民族差別と髪の色の話と大差ないと思います。平然と差別を口にする輩に限って、自分の利害関係が絡んだ時にだけ敏感だったりするものなのでしょうか。
それはさておき、西欧できっぱりと否定されたABO式血液型による性格診断が日本でのみ連綿と生き残り、なぜしつこく流行るのか、と言いますと、その手の話の好きな少女を狙ったマスコミが、「売れれば中身は嘘でも良い」 とばかりに飛びついたからでしょう。
現在日本で語られる、「A型は慎重で...」「O型は大胆」といった話は、日本で出された疑似科学論文に端を発します。心理学という元々が科学と言い切れないものの中でも現在は否定されているような話ですから、疑似的な中での似非科学、King of 疑似科学ですね(^^;)。
西欧で白い目で見られる理由は、これを他国への侵攻の拠り所とした経緯があるからです。
欧州の中央アジアへの侵攻と時を同じくして血液型の研究が始まり、往時の中央アジアに B型が多く、欧州に A型が多かった事と相まって、血液型と人種の優劣に関係を見出そうとしたようです。だから、ABO式だけが問題にされ、RhとかHLA型とかMN型とかが問題にされないのだと思います。 ABO式がこれらの他の形式に優先する理由なんて、発見の先後しか無いと思えるんですけどねぇ(A^^;;)。勿論、これらの古い学説に統計学的な根拠は無く、神話に過ぎないのですが、何時の世にも人は「自分が優れた存在だ」という神話には騙されるものです。
当時は「人種」が生物学的な“種”だと思われていたのか、私は詳しい事情は存じませんが、こんなトンデモ学説と侵略の歴史への反省があって、知的な人は相手にしないわけです。
日本では、あの種の神話を信用する人が多い余り、逆に「自分の血液型はこうだから」とインプリントされる人が多くいるという説もあります。
自分を知的に見せる必要はありませんが、無知が社会差別すら生む元凶となり得るのも事実の様ですから、注意したいものです。ABO式での性格判定は概念的にはいわゆる優生学だって大差ないでしょう?
日本だって、過去に優生保護法と言う過失 (犯罪と言うべきか?) があります。ハンセン病はそんなに古い話では無いです。
他人の心の痛みを理解し、同じ愚を繰り返さないようにしたいものです。
話の発端は、ある、本人以外は誰も書きこまない Blog みたいな掲示板で見た話です。
その話を要約すると、或る将棋指しが髪を染めているのを指して『黒髪は人種、民族固有の特徴であり金髪や茶髪にするのは、川原乞食のやる、見下げ果てたことだ。』
これ自体は、語る価値すら無い、しょうも無い話です。何時も言っているように、私はこの類の輩と議論なぞするつもりは、全くありません。
自分の掲示板で自分の知能程度を披露するのは個々人の勝手ですが、しかし、この種の低レベルの話が、議員やスポーツ界、教育界にも蔓延しているようなので、これはちょっと問題です。
そこで、少し人種と民族について、私見なぞ述べる事とします。そもそも、黒髪が日本民族の特徴などと言うのは幻想に過ぎません。いや、それ以前に、科学的な意味での「民族の身体的な特徴」なんぞ、存在しません。先ずこの話から始めましょうか。
第一に、人種とか民族とは何でしょうか?
こことか ここを見れば解かる様に、社会的、文化的、経済的、政治的慣習と、精神的な同化意識以外に、民族や人種の定義など存在しません。いや、存在する筈がないのです。当たり前です。だって、現存する人類は全て、
哺乳類 - 霊長目 - 真猿亜目 - 狭鼻下目 - ヒト上科 - ヒト科 - ヒト
の、唯一種です。「日本人種」だの「アングロサクソン人種」なんて生物学的な区分は存在しません。
肌の色とか髪の色なんて、その種の分類からは無意味であることも解かっていて、信頼性の在るデータもあります。
つまり極端な事を言えば、もしかしたら隣家のおじさんよりも、フランスの有名シェフの方が遺伝的な距離は近い事だって無いとは言えない、という事です。
この意味で「民族(nation)」ならまだしも、「人種(race)」と言う言葉自体、私は問題があると思っています。それでは、自然科学的な意味以外の意味、つまり社会的、文化的な意味ではどうでしょう?
私の高校時代の友人には、生まれつき髪の色が赤い人とかも居ました。彼らの扱いはどうなるのでしょう? 生まれつきならよくて後に染めたら駄目だじゃ、論拠が希薄です。
今後、国際結婚が増えることはあっても減ることは無いと思いますが、その時、馬鹿な事を言っている輩はどうするつもりでしょう?
「黒髪以外の人と結婚するとは非国民である」とか、更にお馬鹿な事でも言うのでしょうか?(笑)こういう事を言うと、「それは特別な例だ」とか言い出す、血の巡りの悪い輩が居るものですが、特別な例を無視しても良い、なんて浅薄な考えの裏には、唾棄すべき全体主義思想が見え隠れします。
民族主義 -> 国家主義なんて、お馴染みのパターンですね。
言い替えると、その程度の人が その程度の主張をするって事です。例えば、もしも生れつき赤い髪の人が、黒髪に染めても、こういう人は同様に文句をつけるでしょうか?
肉体労働で日焼けした小麦色の肌を見て、「黒人の真似をするな」と怒るのでしょうか?オーストラリアの白豪主義は過去の話ですが、しかし今もかなりの人が金髪に染めると聞いたことがあります。 民族紛争の続くクルド人なんかは差別を避ける為に金髪に染めたりするそうです。 アメリカには昔から "WASP" なんて言葉があります。
基本的にはこれと同じ差別を日本でやっているわけで、色が金色から黒色に変わったに過ぎません。
何も他国の悪しき風習を輸入する必要は無いでしょうに。こんな怪しげな民族主義的思想が蔓延るのも、何時まで経っても近隣のアジア諸国に信用されない理由の一つなんじゃないかい?、と思ってしまうのであります。
HP 開設してから、苦節10年・・・ウソです(^^;)、三年半での達成でした。
意外に早かった、という気がしています。内容的に濃いめというか(^^;)、一般ウケはしないだろうと覚悟しつつも、"科学する心"をテーマとして書いてきましたから。それが、少なくとも多少は受け入れられたのかと思うと、素直に嬉しいです。
まだ書き足りない事は沢山あります。
例えば特殊相対論に触れていながら Maxwell の方程式について全く書かないのも、何処かインチキ臭い気もしてきます(^^;)。
しかし、教科書的な内容そのままでは、自説を自ら否定する事になります。そんなインチキ臭い箇所は沢山ありますが、個人の HP で可能なことなどたかが知れてる・・・と開き直って(^^;)、書きたいことだけ書いていく事にしていますので、これからも宜しくお願いいたします。
しかし、誕生日に達成ってのも、ナンか因縁めいていますな(^^;)。
なんか、また一年近く空いてしまった(A^^;)。
ちょっと趣向を変えて、イメージのお話です。
大体に置いて、日本人は他人と同じであることを良しとする傾向があると、私は思っています。某首相の中身の無い改革イメージで選挙に勝てたりするのはそのせいだと思いますが、他人の描いたイメージすらも、自分のイメージだと思ってしまうようです。その傾向が顕著に現れているのが、高校野球の丸刈りでしょう。あれを見て、一途で爽やかな青少年をイメージするのは、私の感性では“イメージの貧困”なのですが。
無論、坊主頭が悪いなどと言うつもりはありません。それにくっついてくる過去の虚像を、自分の想像とはき違え、更には、その“貧困な想像力”を子供に植え付けようとする姿勢に問題がある、と言っているのです。九州では、虚像を引きずる文化が根強いのか私は知りませんが、未だに坊主頭を学校全体で強要する小中学校が多いそうです。
そう言えば、受け持ちの小学生にイジメを繰り返して、停職になった先生も福岡でしたね。曾祖父が米系なのを「血が汚れている」だのと差別用語で蔑視し、更には執拗な暴力行為を繰り返した先生が“停職”で済む、という感覚自体が、イメージの貧困と言うべきか?世間的常識からすれば、懲戒解雇は当然として、それ以上の制裁すらも妥当と思われる行為でしょうに。大学生の麻薬の栽培と言い、九州在住の方々には申し訳在りませんが、私の九州の“イメージ”は猛烈に悪いです(^^;)。
さて、オーディオほどイメージが先行する趣味も少ないでしょう。
WE 信仰なんぞは その最たるモノですが、数百万円もするトランスポータや DAC なんぞを有り難がるのも、イメージが実像より先行している様に思えてなりません。私には、その中身がどの程度のモノか想像がつくだけに(^^;)。
これなんかも、かなりの部分が他人の作ったイメージを追いかけているんじゃないか?と思えるのです。勿論、それで当人が満足している分にはカラスの勝手で、他人がどうこう言う話では無いのですが、羨ましがるような話でも無い、と言うことです。或る、有名なゴルフの先生がこんな事を言っていたのを思い出します。
「考える、というのは人間にとって辛い行為です。だからこそ、それをやる人がこんなにも少ないのです。」
去年の神有月から一年以上飛んでしまいました。飛びます、飛びます(^^;)。
測定についてお話します。と言っても、「測定値と音質は・・・音が音で音だ〜」なんて話では無いので、悪しからず(^^;)。
正しい測定には、正統な方法があります。正しい値を得るには分解能も必要ですが、測定器の確度も重要です。だからと言って、それで精度が出るわけではありません・・・
先ず、これらの言葉の意味についてですが、JIS C1002に規定されています。一般には「精度」しか使わないでしょうが、しかし測定の精度とは「測定値の正しさ」では無いのです。これは、測定値の再現性の高さを表す言葉です。
これに対して、確度とは普通に言う意味での測定器の「正確さ」です。これには、絶対確度と相対確度があります。絶対確度とは、公的な機関で認められた、標準器に対する測定値の近さです。相対確度は、二次標準に対するそれです。さらに、短期と長期で分かれます。
平たく言えば、お墨付きをもらった校正システムに対するズレですね。分解能とは、測定値を読み取ることができる最小の変化量、とされています。
私の安物歪み率計は、-80dB程度しか分解能が無く、確度も悪いです。これに対して、歪み率計と称する、ある製品があります。-140dBとか、もの凄い低歪みが測れるかのように謳っていますが、メーカーでは全く相手にしない、と言うより、それ以前に測定器と思っていません。何故か?
高調波歪み率の測定は、もちろん規定があります。この歪み率計は、自社独自の方法(笑)なので、規定に合致していないのです。従って、公的機関の標準と読みは合いません。
これは、こちらがメートル表示の物差しで、あっちはフィートなのに、数字だけ比べるようなものです。歪み率計は基本波除去した残りのTHD+Nで測りますが、これはハイパス・フィルタによる基本波以下の成分除去なので、そもそも、帯域幅が定義できません。雑音というのは、そもそも帯域幅で決まるので、これでは比較のしようがありません。
極端な例を挙げると、ハムの混じったアンプの歪み測定では、例えば 1[kHz]で微少レベルを測ればTHD+Nは悪化します。しかし、こういう独自の測定(^^;)だと、どんどん良くなります。つまり、測定分解能がどんなに高くても、確度は「極めて悪い」と言うことです。
但し、信号に対して雑音が無視できる程に低い、相対的に高レベルでの測定で、かつ被測定物が十分に低雑音のアンプならば、ある程度は信頼できるかも知れませんが。結局、私の安物の方が測定器としての確度はむしろ高い、と言う事になってしまいます。
マトモな測定器を設計していたある人に この変な測定器モドキの話をしたら、
「歪み率計と言うのは詐欺だね。歪みモニターと言うべきでしょう」
と言っていました。彼はきっと、かつて校正システムで苦労したのでしょう(笑)。簡単に、雑音と歪み率の例で表しましたが、これは事の本質に関わる問題です。
測定には、他者との比較の意味があります。他者とその標準が違えば、比較できない訳ですから。精度も、分解能と確度が高ければ高いとは言えません。
例えば、ディジタル式の数字で表示するタイプなら誰でも同じ値を読みますが、メーター目盛り式なら読みとり誤差が出ます。
或いは、先に示した歪み率計の例で、基本波除去のノッチフィルタは入力信号と同調を取るのですが、もしも自動同調で無ければ、測定者の熟練如何で相当に結果が異なります。長時間かかる測定の場合には、安定度の問題もあります。
つまり、精度は悪くなります。波形観測ですら、こういう事はあり得ます。
最近のオシロはディジタル・ストレージが多いですが、アナログ式に比して読みとり数値の精度や確度が高いです。私のはアナログなので、波形観測時の値はディジタルのものほどの信頼性がありません。もちろんアナログの良さと言うのもある(例えば、私の本職ならコンスタレーションなど)ので、アナログオシロは駄目と言う意味では無いのですが、例えば真空管アンプで良くある、低出力時の方形波ザグによる低周波特性比較の様な測定には、あまり向かないと言うことです。
まぁ、オシロと言うのは数値を比較する測定での確度や精度は、そもそも低いのですが。
例えば、オシロで雑音を読むなんて誰もできない(^^;)ですし。勿論、プローブの校正などは良く注意しなければなりませんし、ディジタル式ならオシロの帯域幅や測定周波数とFsの関係にも留意が必要です。その上で、精度の高い読みとりの為の熟練が必要になる訳です。
他の例では、電力計もあり得ると思います。
最近は安価な家庭用の実効値電力計を売っていますが、簡単に信用するわけには行きません。その周波数特性が問題になり得るからです。電力計は50/60Hzだから関係ない、と思われるかも知れませんが、通常の電子機器は全てコンデンサ入力整流で直流を得ています。
この時に、電流の高調波は相当な高周波成分まで含んでいます。特にディスプレイやTVならトランス無しでACを直接整流しますから、尚更です。大抵のスイッチング電源装置もそうです。 (電源トランス付きなら、それ自身の漏洩インダクタンスで高周波を通し難いので、かなり楽にはなると思います。言い替えると、力率が良くなると思います。)自分の測定値とメーカを含む他人の測定値を比べたいのでしたら、確度の高い測定器で、精度の高い測定をする必要が出てきます。
雑誌の記事などでも相当に怪しい測定結果が出てくる事がままありますが、測定している人には悪気が無くても、測定結果が正しいとは限りません。勿論、メーカがそんな事をやれば、悪気は無くても訴えられますけど(^^;)。それでも私は、いわゆる四畳半オーディオメーカの測定データには、最初から眉に唾を付けながら見ることにしています。
2001/10/28 神有月弐拾八日 般若心経とシュレディンガーの猫
量子力学で量子の‘重ね合わせ’というヤツがあります。言葉で上手く説明するのは難しいですが、状態 A と B が同時にあるような感じと思って下さい。
確率波が収縮する以前(観測するまで)は、波動関数での確率的な波は「同時に、あっちゃにもこっちゃにもいる確率」みたいな感じです。(コペンハーゲン解釈ですが。)これを、最も端的に漢字にするなら「色即是空、空即是色」、これしか無い。
エヴァレットの多世界解釈なら「無眼界、乃至無意識界」、これでしょう。二千年も前に釈迦牟尼は量子力学を予言し、摩訶般若波羅蜜多心経には真理があった!!
仏教哲学の深遠さは、必ずしも方丈(ほうじょう)さんに聞かなくても、現代物理から解るかもしれないですよ〜 (ない、ない ^_^;;)。「シュレディンガーの猫」という有名なパラドックスがあります。簡単に言って、その重ね合わせ量子で、猫といっしょの毒のビンを割ったらどうなる?て話です。
で、その猫は、「生きて、かつ死んでいる」重ね合わせ状態の中で般若心経を唱えていた...訳ではありません(^◇^;)。毒のビンが割れるか否かを、実験する人は観測していなくとも、当の猫本人、いや本猫(ほんびょう)か、は観測しているのですから。
所で、そのパラドックスに付いて、「シュレディンガーの猫」という本があります。その挿し絵を見ると、どう見ても日本の「まねき猫」に見えます。
その日本の固有種である日本猫が、絶滅の危機にあります。これは本当の話。トキが死滅する、とか言って繁殖計画を国が躍起になってるのに、何で純血種の猫の繁殖をやらないんでしょうね?日本オオカミの純血種は途絶えましたが、もし今見つかれば、大騒ぎで繁殖計画が練られるだろうと思いませんか?(犬の中には雑種が沢山いるでしょうけど)
それなら、雑種化して純血種のいなくなった日本猫だって同じでしょうに。こたつの中で丸くなったり、ひなたぼっこしている‘タマ’みたいな日本の伝統的な風景は、既に過去のものとなりつつあるようです。
私は日本人ですから(^^;)、欧州の城みたいな家で貴族的な生活なんかよりも、長い縁側のある家で日向ぼっこする田園風景に遥かに心を惹かれます。そこにタマが居ればもっと良い。
タマアンプがあれば更に。(嫁がいれば最高ですけど(A^^ゞ))これって、高々ここ数十年の話でしょうから、日本人の不思議さを端的に表している様にも思えます。トキと猫の価値観の差って何なんでしょうね?値段でしょうか?
漱石の「我が輩は猫である」は黒猫でしたが、あれを読んで感動できる世代がいなくなってしまった時に、純朴な日本人の心もまた絶えるように思えてきます。
最近、ある世界的に著名な日本人のソムリエが、新聞に「究極のラベル汚れ (^^;)」とも言えるような話を書いていました。
このページの少し下にラベル汚れのワインについて触れていますが、ラベル汚れでも美味いワインがあるって話は、何も私の個人的な感覚の問題(味覚の貧しさ ^_^;)ばかりでも無さそうなのです。良く知られているように、ワインは涼しい場所で、日光を避けて、横に寝かせて保管されます。これを守らないと、とんでもない目に遭うと信じられています。その逆を試した人は少ないようです。無謀にも、これを試した人のお話。
直射日光にあたる場所で、しかも立ててかなり長いこと保管したらしいのですが、そのワインが驚くなかれ、「シャトー・ラフィット・ロトシルド」!!!!
これはボルドー赤ワインの四つの一級格付けのうちのひとつで、しかも60年代というから、我々ビンボー人には清水の舞台から飛び降りても飲めません。
(この1855年に作られた「メドックの格付け」と呼ばれるものも、それ自体が問題を抱えているらしく、良心的なシャトー必ずしも・・・という話もありますが、まぁそれは別の問題です。)因みに、この種のワインは若い(熟成されない)うちは、タンニンの渋みが強くて飲めないのですが、熟成を経てそれがまろみに代わり、芳醇な味と香りを育てます。(この種のワインを若いうちに飲むことは「文化的な犯罪」なんて言います。)
その為に、作るときからして、ブドウを「濃く」します。具体的には、量産ワインは一本の木から数ビンのワインが出来ますが、この手の超一級シャトーものは、一本の木からビンに半分も作られません。
つまり、剪定によってブドウの木の力(気の力?^^;;)を少ない房に集めるのです。フランスはシャトーもののワインの質を守るための法律がありますが、そのAOC法で定められた単位面積あたりの収穫量を遥かに下回る量しか作られないのです。そんなものをテキトーに保管したのも凄い話ですが、そのトンデモ・ロトシルド(^^;)を飲んだら、「完全に熟成した極上の白ワイン」だったそうです。
日光が当たる場所で立てていたものだから、色が落ちて沈殿してしまっていたそうです。これはもう、ある意味で究極の贅沢かも知れません。きっと今後、同じ事をする人は絶対に居ないでしょうからね。それはともかく、この事が示すのは、我々ビンボー人はラベル汚れを恥ずかしがらず堂々と買うべき、ということです。もしかしたらもの凄い「大当たり」を引く可能性なきにしもあらず、なのです。
先ずは自分の舌を信じませう(^^;)。誰のためでもなく、あなた自身のために。
尚、最初に神有月とあるのは神無月の誤りではなく、私の生まれた地域では神有月(かみありづき)と言うからです。拙は神有月の生まれですから。
首記の題名の本(太田出版)が出版されているので、例によって戯れ言などをば。
なかなか面白かったけど、最後にもの凄く面白いあとがきがありました。
なんと、最後の方に、私のHPの一文が載ってたんですな。やった、メジャーデビューだ・・・じゃなくて(^^;;)、それは当HPへの批判的な内容です。
先ずはここを読んで貰わないと、話が通じないんですが、この一文に対して、
『「僕は光が電磁波の一種じゃない」なんてバカなことを書いた覚えは無いのだが・・・』
との山本氏のコメントがありました。そりゃあ、私だって、そんなの読んだ覚えがないわ(爆笑)。
私が言いたかったのは、質量の方の話で、質量の無い電磁波が光速度を越えないのは、「質量が無ければ」と言う話に矛盾しますよ、って事だったんですけどねぇ。だから「二重に」と言ったのは、情報の話と質量の話という事です。
取り敢えず、私の文章力の問題は棚上げにするとして(^^;)、何でこんな誤解が生まれたかと言いますと、要するに日本語での解説の限界じゃあ無いでしょうか?
じゃあ英語ならっ・・・て話じゃないですよ(^0^)、勿論。
問題は、数式で表された内容を普通の言葉で説明することの難しさです。基本的に、物理学に限らず、自然科学の言葉は数学的なものです。最も簡潔かつ明瞭に、しかも誤解の無いように書くには、我々は他の言葉を持たないからです。
私は、数式の変形なんかよりもそれを直感的に理解し、その人なりのイメージを描くことが重要だ、と言ってきましたが、勿論それは式無しでも良いという意味ではありません。
「式を理解する」事が大切だ、と言ってるのです。皆さん、厭がらないで、是非。
最近、お金がないので(^^;;)安い酒に凝っています。
私は、基本的にはワインが好きです。
ビールも飲みますが、これはアイリッシュ・ギネスか、ピルスに限ります。さて、日本に入っているワインには各国のモノがありますが、上はロマネ・コンティから下は500円のテーブルワインまで様々です。
一般的に、有名で高いワインを特に安く売っている場合には、「ラベル汚れ」が多いです。
これは、赤道直下を船便で通過するので、冷蔵コンテナ以外では、中身が吹き出す事があるためで、本当にラベルが汚れているから安いのではありません。冷蔵せずに船で送るから安いのです。勿論味は一段落ちます。因みに「裏ラベル」と言うのもありますが、これはラベル汚れとは全く別物です。
もし、これが手に入ったら、あなたはかなり運が良い! ロマネコンティ同等品が5万円ぐらいであります。(十分高いという気もするけど。^^;)でも、最近はラベル汚れすら買う金が無くて、フランスワインやイタリアワインはとんとご無沙汰。かわりに、あまり知られないワインが多いです。
その中での最近の最近の「ヒット」をご紹介しましょう。
つまり、C級テイスティング物語。(^^;;)1.C/Pでは、何と言ってもカリフォルニア・ワインです。\580で買ったワインが、意外に飲めるので驚きました。少し香りが悪いですが、我慢できないほど非道いものでもないです。
サントリーが「フランジア」と言うのを輸入しています。軽い味で、ライトボディの若い赤。2.\1200ぐらいしたので、最近の中では高価(^_^;;)ですが、スペイン産の「シグロ」はナカナカ侮れないモノでした。香りのすばらしさは、かなり良いイタリアワインとタメをはります。ミディアムボディの赤でしたが、嫌みが無く、すっきりしています。ヘビーな料理とも合いそうです。
3.チリ・ワインもかなり入ってきていますが、香りに問題がありますね〜。
でも、その中でメルロー種のものは、まぁメルロー系の味だという感じはしますな。メルロー系が好きなら良いでしょうが、一般的にはカルフォルニアの方が良いんじゃないですかね。4.ニュージーランド産もかなり入ってきています。はっきり言って、今まで飲んだのは全て「大ハズレ!」(^◇^;;)。
特に香りの悪さは一級品(^^;)と言っても良く、何か下品な感じが付きまといます。大体に置いて、大手の輸入したモノで、マシなのはあまり無いようです。(^^;;)
小さい所が良いものを安く輸入する傾向があるのは何故でしょうね?
そういうお店で、「ムーラン・ナヴァン」(ボジョレーの王と呼ばれています)を\2500で売っていました。それを横目で見て「あぁ、飲みたいな〜」と思いつつ、今日もカリフォルニアを飲む‘かつ’であります。(^^;;;)
理系大学生の学力低下が叫ばれる中、朝日新聞に授業への「興味」についての調査結果(京大大学院教育学研究科研究生で静岡県の高校教諭渡辺一利さんによる)が出ていました。
要約しますと、ほとんど全ての理系教科に興味があり面白いと答えたのは僅かに29%、授業内容の半分以上がつまらない感じている学生で35%、一部についてでも面白さを感じていないのは36%だそうです。
これに対して、高校時代に物理が好きだった学生は74%に達するとの事。これは、その名にしおう京都大学理学部での数字ですから、全大学の理系で調べればさらに悪い結果が出ると考えられます。
この結果に対して、高校側の意見と大学側の意見の差が際立っています。
前述の渡辺さんは
「高校までは理科が好きだったはずなのにこれだけ興味が薄れているのには驚いた。我々も大学に合格させるだけではなく、先を見た教え方をしないといけない。大学の先生ももっと教育に目を向けてほしい」
(朝日新聞社、3月19日付け asahi.comより引用)
さすがに高校側では、誰が主人公なのかを良くわきまえておいでです。対して、京大理学部の教授は
「実感と変わらない結果だ。大学側にも責任はあるが、大学の授業は高校までとは違う。昔の学生は内容の差にショックを受けても立ち直って追いつこうとしたが、今はそうではない。勉強の仕方から教えなければならない」
(同じくasahi.comより引用)
と阿呆なことを言っているようです。これは言い方を替えれば、
「学生が理解できないのは、最近の学生ががアホだからで、こっちは悪くない。だから、今まで通りのやり方で通用させる為に、学生の方を修正したい」
と言っているのと同じです。
どうやら、大学教授に「自己改革」という言葉は存在しないらしい!私は、かねてより理系大学での授業にこそ問題があるのであって、それを改革しなければ日本に未来は無い、と主張してきましたが、これはその強力な証拠であると考えます。
もしも、高専で同じアンケートをとったらどうなるか?かけても良いけど、逆に近い結果が出ると思います。
ついでに書いておくと、もしも京大の物理学系と高専の電気科で、同じ問題で「電磁気学」の試験をすれば、絶対に後者の方が良い点を取ると思いますよ。つまり、問題は学生の質ではなく、授業(講義)の質なのです。それがここに来て露呈したというだけです。最悪なのは、大学教授はその事を全く認識していない、ということ。
上述の阿呆な教授の言うように「高校と大学の授業は違う」のではありません。「あえて、違えている」のです。第一、高校での授業が現在の様に大学との一貫性に乏しいのは、高校のせいでは無く、そういう入学試験を大学側がやっているからでしょう。高校側がそれに追随するのは当然のことですし、そのそも高校の教育課程を定めているのだって、高校教諭が決めている訳ではなく、「有識者」の名の下に大学教授がしゃしゃり出ているではありませんか。
事実、こういう問題は欧州などでは全く聞きません。
私は、仕事で欧州の研究者や技術者と話をする機会が多い(仕事のメールでは大半を占める)のですが、私と関係がある電気/電子/情報系で言うと、例えば特殊相対性理論が理解できないエンジニアなんて居ませんでした。
あんなことを、わざわざ説明しなけりゃならんのは、日本ぐらいのものです。
電子系では物性を扱う為か、一般相対論すら理解していました。(私自身は授業ではやっていません。単なる趣味です。プラズマ物性論は授業でやってるんだから、変な話ですが。)私が大学を出たのは既に随分昔の話ですが、ここに来て問題はより顕在化してきた、という事でしょう。
これは、最近の若い人が孤立化してきた事と関わりがあると考えます。昔は、解らなけりゃ解る人に聞いたもんですが、自己を主張するばかりで外部との関わりを極度に嫌う最近の風潮が、間接的にこの結果を招いているように思えてなりません。
と言うのは、同じ日の同じ新聞に、最近の卒論(多分文系?)は自分の事ばかり書いてあるみたいな事も書かれていましたから。そこで、提案です。
大学教授の「教え方認証資格試験」を設けてはどうでしょうか?それも実際に学生を使って授業を受けてもらって。何の資格も持たない人が「教育」を行う事はそれ自体おかしな話です。
また同時に、研究成果と同等以上の評価を教育に対しても与えなければ、だれも実践しないでしょうから、評価待遇の改善も必要です。誰も理解出来ない授業は、どんなに内容が濃い物でも、その存在価値など無に等しいのですから。
立花 隆氏の大著「臨死体験」(上/下:文芸春秋社)を読んでみました。さすが、立花氏は現代日本における知的巨人と言われるだけの事はあって、その膨大かつ広大な知識と詳細な調査には驚くばかり。
さらにそれを感情に流される事無く冷徹な目で見つめる分析力は、「ジャーナリストかくあるべし」と思わせました。「社会現象」の話で触れたようなマスメディアとはエライ違いです。「科学する心」を持って一つ一つの事件に接し、自らの感情、感覚と冷厳なる事実を明確に区別してらっしゃいます。
私自身は「臨死体験」したことは無い(そりぁそうだ^^;;;)のですが、臨死体験者がそうでない人よりも、より生を大事にし、かつ死を怖がらない、と言う一見すれば矛盾する内容には考えさせられるものがあります。
逆説的に言えば、一般には死を怖れるばかりで、生きる事の価値とか生の意味とかを考えていない人々−はっきり言えば無為な人生を送る人々−が大多数である、という事なのですから。これとは別に、もう一つ面白い点があります。
詳しくは読んで欲しいのですが、立花氏は、臨死体験−特に体外離脱について−は脳内の現象なのか、それとも現実的な現象か(つまり「魂」があるのか否か)について色々論じてらっしゃいます。
これは研究する科学者も両者に分かれているようです。立花氏は脳内現象説に傾いているのですが、その論拠は完全に見えないモノを見たような数少ない場合でも、それは「目」意外の場所で「見て」いるのだ、ということのようです。(レアケースではあります)
しかし良く考えてみると、逆に脳内現象説を採る限りESPを認めざるを得ないケースがある、と言えるわけです。どちらに流れてもオカルトじみて聞こえますが、どちらもオカルトではなく、何をもって「魂」とするのか、何をもって「ESP」とするのか、という根本的な部分で我々人類の科学的な知識が無いからに過ぎません。
我々の脳のどの部分をとっても、「自我」の座というか、CPUで言えばALUに属する部分(例が悪いか?^^;;)は見つかっていません。結局の所、脳内現象説は魂説に懐疑的に反駁することは出来ても、積極的な説明は出来ていないのです。
ESPにしても、例えば脳が発する電磁波を別の脳が直接受け取ったとすると、まさしく「遠隔認知」には違いないのですが、なんか普通に言う超能力とは違う、科学的な話にも思えてきます。
でも、霊能力云々の怪しげな話をする人達とは何が違うのか、と言えば結局のところ、本質は「解らない」が答えです。この点で言えばさしたる違いは無いのです。関連する話として量子論の大家、梅沢博臣・アルバータ大学教授の「量子脳力学」の話が出てきていますが、無論これも仮説に過ぎません。(しかし、今まで非科学として切り捨てられてきた部分に科学の日を当てる、と言う意味で価値があるとは思いますが。)
ところで、「と学会」の本で皆神氏が「臨死体験」の内容の一部にいちゃもんを付けている部分があります。
しかし、どうやら「SI誌」の話をそのまま無批判に写しているだけで、詳細に実地調査した立花氏の話を批判するという、つまりトンデモの手法に過ぎない様です。(さらに皆神氏はこの話を「立花氏が信憑性が高いと書いている」と言っているが、「臨死体験」にはそうは書いてない!)正しいか否か、が科学とトンデモの区分けではありません。こういう皆神氏のような姿勢こそが、トンデモとして糾弾されるべきものと思います。これは疑似科学的な疑似科学批判であると考えます。
懐疑的になるべきは、必ずしも怪しげな話ばかりとは限らないのです。
社会現象とか、社会的な問題とかを議論する最大のメディアは、新聞でありTV・ラジオ等の放送メディアであることは論を待たないでしょう。
これらは読者数や視聴者数から言って、未だ、所詮はインターネット等は敵ではありません。問題は、大新聞や某公共放送をはじめとするビッグマスメディアが、科学する心を持たないという恐るべき現実です。さらに、我らが意志決定機関である政府も、我が日本の立法府たる国会すら、これを持たないのです。
少年法改正案が衆院を通過しました。この改正の最大の理由は何であったかと言えば、一口に言って、激増する凶悪な少年犯罪に対する歯止めとしての厳罰主義、という事でしょう。
では、近年において少年の「凶悪犯罪」、つまり殺人ですが、本当に増加しているんでしょうか?
実は1970年代以降はさして変わっていません。それ以前はと言えば、もっと多かったのです。
理由は明白、「衣食足って礼節を知る」です。経済的に豊かになったから。もっとも、現在は子供の数が少なくなっているので、明らかに子供の数に対する率としては上がっていますし、最近はその犯罪の理由が不条理なものになってきた、と言うのは事実です。
つまり、殺人の理由が経済的なものでは無くなってきています。議論するとしたらこちらであって、「増大する凶悪な少年犯罪」では無いのです。
しかし、不条理な理由に対して、何故厳罰主義なんでしょうか?理論的に考えるなら、彼らに条理を求める、つまりしっかりした再教育こそが求められるべきでしょう。私が何を言いたいのか、既にお察しでしょう。
簡単に言って、彼らは雰囲気に流され、自分の感情を論理とはき違えているのです。「WEの真空管とアルテックでなければ真の音楽は再生出来ない。何故ならそう感じるから」 これと同じレベルの議論が、堂々と国会で論じられた、という信じがたい事実に驚愕したのは、私だけでは無いと思いたい。
データをもって反論できないのなら、勿論それは科学ではありません。
凶悪犯罪の理由であれ、真空管の音であれ、統計的処理をもってデータで論じることは可能なのに、それを行わずに情緒に流れて本質を見ていません。つまり、オーディオ評論家と全く同じレベル、速く言えば「トンデモ」なのです。私は、かねてより「社会科学は今もって疑似科学である」と断じてきましたが、それが再び証明された、と言うことです。敢えて、遺憾ながら、と言わせていただきます。
今必要なのは、やはり教育、それも「科学する心」を教育することじゃないでしょうか。
何故なら、政府の宣伝やマスメディアに踊らされない為には、今、我々こそがしっかりと科学する心を持つ以外には無いのでは、と‘かつ’は信じるからです。
白川教授がノーベル化学賞を受賞したことを、先ずは素直に喜びたいと思います。
所で、今年のノーベル賞は、何だかいつもと違う感じを受けました。白川教授の化学賞もそうですが、私はそれ以上にジャック・キルビー博士の物理学賞に驚きました。
キルビー博士は、何と言ってもICの基本特許で有名(俗に言うキルビー特許)です。いわゆるサブマリン特許であったために、日本でも大騒ぎになったので、ご存じの方も多いと思います。両者の共通点は、「高い実用性を有した発明・発見」であった、と言う点です。この点で一昔前の福井教授の化学賞とは大分ニュアンスが違うように思うのです。
私がこのHPで、スウェーデン王立アカデミーを非難したからに違いありません・・・ってそんな訳があるか!!(^^/
冗談はともかく、ノーベル賞の精神からして、私はこれは健全な方向だと思います。
血の巡りの悪い人が勘違いするといけないので書きますが、実用性のない発明・発見に意味がないと言ってるのではありませんし、言うまでもなくアメリカ流のサブマリン特許を肯定しているわけでもありません。
基本的な科学の発見なんてものは、殆どの場合にいつかは役に立つものです。これは今までの科学の歴史を紐解けば明らかです。私が言ってるのは、ノーベル賞の精神です。アルフレッド・ノーベルの遺志です。
ノーベル賞が世界最高の権威を持つ賞であるのは疑いのないところですが、そんなもの、ノーベルの遺志ではありません。彼が欲したのは、名声ではないはずです。今の科学は、昔の様に大学が産業界と一定の距離を置いて、孤高を保った象牙の塔からものを言う時代では無くなりました。
アメリカを始めとして、産業界と学会が一体となって、ある目的の元に基礎研究を行う時代です。遅蒔きながらも、スウェーデン王立アカデミーがこの事に気づいたのは、とても良いことだろうと、私は思っています。
エコロジーの時代、この精神無くして、時代を乗り切ることは困難でしょう。
我々の孫〜曾孫の時代につけを回さないためにも。
DIP(Dual Inline Package)のICって、何だかムカデに似てますな。自慢じゃないが、‘かつ’は三回もムカデに噛まれた事があります。その三回とも種類が違います。というわけで、オーディオには何の関係もない、毒の話です。
ムカデは、節足動物−唇脚(シンキャク)類に属し、一見、良く似たヤスデとは類が異なります。ヤスデは毒を出すけど、噛み付かないので心配無い。これは毒と言うより、臭いだけでカメムシと同じです。
ムカデと言うのは、強い毒がある上に、狂暴で、体に触れればすぐに噛み付くし、脚にも毒があるのか、歩いただけで腫れ上がる人もいる。肉食ですが腐食性があるので、噛まれると破傷風等の可能性もあり、特に子供には要注意です。
ムカデは、毒の強さ(と言うか、痛さ)でいうと、スズメバチなんか目じゃない。かつはスズメバチにもアシナガバチにも刺された事があるので間違いない。(スズメバチよりアシナガバチの方が痛かった。)
噛まれたうちの1回はオオムカデ種のトビズムカデで、これは体長10cmクラスの幼体でした。オオムカデは世界的に見ても最大クラスのムカデであり、最大20cmにも達します。昔、住んでいた家が森林公園の裏にあったせいで、夏になるとムカデが家の中にまで現れました。実際、20cmクラスを家の中で見た事があります。あれは恐いですよ〜!
もう一回は,体色が白いヤツで種類が解らない。田舎で噛まれました。サシキリとか何とか昔は言っていたように記憶しているけど、あまり定かじゃないです(方言かもしれない)。ゲジの仲間(あれもムカデの一種)は白っぽいけど、脚の数が少ないので違う種類だと思います。オオムカデの脚は21節42本、ゲジは15節30本。漢字で百足と書くわりには少ない?いやいや、イシムカデの仲間は177節あるやつも居るらしいです。
因みに、英語ではcentipedeと言い、centとはセンチメートルのcentで百、pede はペダルのpedeで脚の事。まさしく百足。ヤスデは英語でmillipede。つまり千足。ヤスデの脚は千鳥状になってるからだっ?んなアホな!
アカムカデ(オオムカデの亜種で最大でも8cm以下)にも噛まれたが、あれは小さいだけに大した事は無かった。痛いには痛いのだが。
カラフルなムカデを見た事があります。黄色と緑っぽいヤツ(キモチワル〜)。他にアオズムカデって名前の青いのも居るから、赤、青、黄と信号機風(?)ですな。(^^;;
困るのは、ムカデはやたらすばしっこい事。ゆっくり歩いている事が多いけど、追い立てるとものすごいスピードで走る。体が平べったいので何処にでも隠れてしまう。しかも力が強い。20 cmクラスが出現した時に、ビリヤードのキューのグリップエンドで押さえつけたら、引っ張られたので驚きました。きっとカブトムシより強いと思う。(^^;;
ムカデは脱皮します。脱皮しているのを、昔、ガキの頃に見た事がある。新聞配達のアルバイトをしている時に、玄関の前に脱皮したのがいたのです。
日本本土で、噛まれて最も毒の強い虫のたぐいはムカデだと思うけど、他に困るのが前述のアシナガバチやスズメバチも狂暴です。アシナガバチは痛いけど、スズメバチは集団で襲って来るので困る。中でもオオスズメバチはおまけに肉を食いちぎるらしいから始末に負えない。
オオスズメバチよりもキイロスズメバチの害を良く聞くのは、季節によりオオスズメバチがキイロスズメバチの巣を襲うために、その時期に近づいて来るものは何でも攻撃するから、らしいです。
(このあたりは、聞きかじりの話が多くて、あんまり定かじゃない。)毒の強さだけなら、アオバアリガタハネカクシ。名前のとおり、蟻の形をしていて、サイズも蟻ぐらい、体色はオレンジ色、羽が青くて、普段は羽を隠している、ハネカクシ科に属する昆虫です。これは歩いただけでかぶれるし、間違って体液が付てしまって、すぐに石鹸で洗って軟膏を付けても1ヶ月近く苦しみました。(実はこれにもやられた事があるのだ。かつは毒虫に縁がある?)
日本には毒のある蜘蛛はあまり多くはいません。強いのはカバキコマチグモぐらいのものかな。ススキの葉を巻いて巣を作り、産卵します。これはすごく痛いらしいから、ススキの葉を、三角おむすび状に巻いてあるのを見つけても、ほどかないようにしましょうね。子供が、何だろう?と思ってよくやられるようです。かなり痛いらしい。
セアカゴケグモが一時有名(?)になったけど、あんなもん、別にどうって事ないって話です。
日本原産のカバキコマチグモの方が強いぜ!昔、住んでいた東京都八王子市で巣を見つけた事がある。因みに、世界的に見て、人を殺せるぐらい強い毒のある蜘蛛は、たしか南米のクロゴケグモとオーストラリアのシドニーツチグモだけの筈です。有名なタランチュラは、実はそれほどでもない。007の映画で騙された人が多いようです。
バードイーターってタランチュラの種類は、その名の通り雀なんか食うらしいけど、毒は大した事ない。
クロゴケグモも、死亡例は数例ぐらいしか無い筈ですよ。毒は強いけど、量が少ないから。だからほんとに恐いのは、シドニーツチグモぐらいか。それより、熱帯雨林に住むヤドクカエルの仲間で、特に強い毒の3種類の方がツチグモの百倍も恐い。
えっ、カエルに毒?って思う人も多いでしょうね。
中でもモウドクフキヤガエル(猛毒 吹き矢 蛙)ってカエルは一匹で人間を二百人近く殺せるだけの毒を持つらしいですよ。触っただけでも、命にかかわる。なんと日本で飼ってる人が居たりするから、はた迷惑な話ですなー。万一、地震で飼育ケースが壊れたりしたら、どないするつもりやねん?日本に居るカエルだって毒を持ってますよ。ヒキガエルは目の後ろの瘤(耳線)から毒液を出しますし、アマガエルは皮膚から毒を出します。何れも大した事はないけど、触ったら手を洗いましょう!
他に両生類では、イモリや山椒魚。イモリの皮膚から出る毒は(微量ですが)、フグ毒(青酸カリの千倍と言われる)の一種だそうです。(おぉ恐い) でも、不思議と蜘蛛を怖がる人の方が圧倒的に多いのは、見た目のせいか?それとも007のせいか?
毒のあるヘビは日本にも何種類か居ます。マムシは誰でも知ってるでしょう。ヤマウナギなんて申しまして、食用にする地域もあります。ハブもマムシもクサリヘビ(Viper)の仲間で、出血毒です。
他に出血毒の種類では、ヤマカガシが居ますわね。昔はそこらじゅうに居たモンですが、最近は見かけませんな。実は、結構強い毒を持っているのですが、性格はおとなしくて、滅多な事では噛みません。
わりにデカイ蛇なんですが、大人しいので、子供の頃、捕まえて遊んだ経験のある人も多い筈です。
これは首筋の所からも毒を出します。奄美大島とか沖縄諸島とかにはウミヘビ科やらコブラ科に属するヘビも居ますが、本土にはマムシとヤマカガシだけです。ウミヘビやコブラは、同じ毒でも神経毒で、痛いとかいうよりも噛かまれると窒息して死んでしまいます。
八重山諸島にはヤエヤマサソリというサソリが居るらしい。日本には他にマダラサソリというのが小笠原に居ると聞いています。他に九州にはサソリモドキの仲間が居るようです。どちらも毒がありますが、大した事はないらしい。(聞きかじりなので定かではない。刺されて死んでも責任は持てません^^;;)
因みに、サソリなんて言うと、刺されたら瞬間的に死ぬようなイメージがありますが、サソリの種類で数時間以内に人を殺せる程の強い毒を持つものといえば、たしかキョウトクサソリぐらいのものだったと記憶しています。
因みに、全てのアリさんは毒を持っています。実はお尻に針がある。あんまり小さいから、関係ないってだけです。でも、ちくっとした事がある人は多いのでは?
ダニ、カ、その他の吸血性の昆虫類には毒がありますが、普通はまぁ、痒いだけ。ダニの中で、幼虫のツツガムシの媒介するツツガムシ病はかなり恐いです。直接的な毒ではありませんが。
毒蛾は痛いですな。あれは幼虫の方がきつい。ガキの頃、背中にくっついて非道い目に会いました。これも何処にでもいました、昔は。
また、さほど攻撃性はないけど、ベッコウバチやマツモムシは結構な毒がある。クラゲの種類も毒を持ちますわね。種類にもよるけど、結構痛いです。世界には、人が数分以内に死んでしまうほどの強い毒のクラゲも居るらしいです。きっと食用にもならないでしょう^^;;。
他に強〜い「毒」のある物と言えば・・・貴方が今、読んでいる‘かつ’の話だったりして。
現在、殆ど全てのディジタルオーディオ機器と、高級カーオーディオ機器に直熱三極管が使われている、それもガラス管が使われてる、と言ったら驚かれるでしょうか?
「嘘だ」「一部マニア向けの悪趣味な商品の事で、ほぼ全部ディジタル機器なんて事は無いだろう」なんて声が聞こえてきそうですが、これは厳然たる事実です。ほとんどのディジタルオーディオ製品に使われているのです。
それは、蛍光表示管(FL管 or VFD とも言います)です。
蛍光表示管の原理というのは、実はガラス封止した直熱三極管そのものなのです。原理図を下に示します。ご覧のように、直熱三極管のアノード(プレート)に蛍光体が貼り付けてあり(パターニング)、フィラメントから照射された熱電子をグリッドで制御し、その熱電子がアノードに当たる時に蛍光体が発光します。
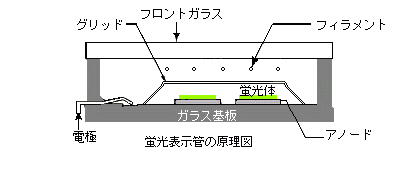
ゲッターは表面からは見えない隅っこにあります。そりゃ表示管でそんなもの見えちゃ困りますわね。
鏡面に輝くゲッターにこそ真空管の息吹を感じる、という向きには、感動が薄いかも知れませんが。フィラメント材質は基本的にはタングステン合金ですが、各社、様々なブレンド(合金)を作って、いろんな問題への対策としているようです。
当然ながらグリッドは発光する部分毎に別になってるし、アノードも部分毎に別ですから、双三極管ならぬ、共通カソードの超マルチ三極管です。
最近はLCD(Liquid Crystal Display;液晶ディスプレイ)を用いたもの(各社ローコスト機に採用)や、EL(Electro Luminance)ディスプレイ(パイオニアのカーオーディオ)等もありますが、依然として視野角の広さ、発光の美しさ、寿命、動作温度範囲等の点で総合的には蛍光表示管に一日の長があるようです。
特に発光が綺麗で表示が鮮明な点が買われて、オーディオ機器やビデオ機器で主に使われていますが、車の時計なんかにも、視認性と信頼性の高さからよく使われます。
ELディスプレイも自発光ですから視野角は問題無いし、電力効率が著しく高いという長所が有るにせよ、寿命が短いという欠点があります。(LCD は基本的には透過型で、光って見えるのはバックライトです。)
「直熱三極管の寿命が長いの?」という疑問を持たれるかもしれませんが、驚く無かれ、蛍光表示管の寿命は3万時間を超えます。
技術の進歩をなめちゃいけません。そもそも、放送局用の直熱型のセラミック管の寿命だってそんなモンです。
しかもこれは、最初の発光輝度の半分になる時間(普通の真空管で言う所の‘球がボケる’迄の時間)であって、フィラメントが切れる迄の時間ではありません。これに対してELディスプレイは長いものでもせいぜい2千時間ぐらい(輝度が半分になるまで)ですから、蛍光表示管は圧倒的に長寿命です。フィラメントの点火方式は、ホームユースでは交流点火が普通で、車では小型の時計みたいなものは直流点火、カーオーディオでも大型ディスプレイに用いたものは交流(パルス)で点火しています。
何故かというと、直流点火では、長いフィラメントにグリッドから見た電位勾配が出来るため、小型なら問題無いけど、大型のものだと発光にむらが生じるからです。輝度に関しては、通常はダイナミック点灯と言って、マトリックス状に配したグリッドを一定時間おきにスイッチングする方法を採りますから、そのON/OFFのデューティーと、マトリックスをなめる時間周期でもって決まります。早い話が明るくしたけりゃONする時間を長くせよ、って事です。
勿論、アノード電圧やグリッドのON電圧、フィラメント電圧なんかでも変わるわけですが、それは寿命に著しい影響が有りますから、普通はやりません。真空管のコンピュータが廃れてから幾年月、1965年に蛍光表示管の原理が発明され、現在の平面型が生まれたのが73年、今やカラー表示が可能になりました。
しかし、真空管コンピュータで問題になり、その時代に解決を見た真空管のスイッチング動作に伴う問題解決の技術は、今も脈々と生き続けているのです。今度、秋葉原かカー用品ショップに行ったら、ダブルDINサイズでやや高額(と言っても10万以下)なカーオーディオをよく見てみて下さい。KENWOODの製品が、カラーの大型VFDを使っているので解りやすいと思います。
電源をOFFして、よくよく目を凝らしてみると、極細のフィラメントが蛍光体の前に見えたり、文字通り格子状のグリッドが見えたりして、確かに直熱三極管であると納得できるでしょう。
球のアンプの30Wは石の50Wから100Wに相当する・・・
昔から言われていた事ですが、何故か?という問いに対しては、不幸にして明確な意見を目にした事はありません。
オーディオ誌に出てきた意見としては、曰く、必要な帯域だけなので人間が注意して聞くだの、曰く、歪み成分が多いから出力が大きいように聞こえる、だのはっきり言って的を射た発言とは思えません。
少なくとも科学的な論拠ではない。つまり実験的実証も、理論的整合性も無しと言わざるを得ないでしょう。私が考えるに、これ、理由は明らかであると思います。
球アンプの最大出力は、8Ωとかで規定される訳ですが、ここに4Ωの負荷を繋げば、最大出力は小さくなります。
石の場合は逆に大きくなります。
何故なら、石のアンプは最大出力電圧で出力が決定されるから。電流はいくらでも・・と言えば大袈裟だけど、まぁ必要なだけはとれる。だから負荷が重くなっても、同じ出力電圧を発生すべく電流が流れるから、出力は大きくなる。
しかし、球アンプの場合はこうは行かない。だから負荷が重いと、出力が減る。「そしたら、球の方が不利やないけ?」と思うのは素人。
スピーカーのインピーダンスは、普通一般には、最低インピーダンス--大概はf0付近にある--で決めているのです。
従って、大部分の帯域では、インピーダンスが高い。周波数で平均すれば、モノにもよるけど、たいてい倍以上あります。フルレンジなんかだと相当上がります。すると、この場合は、最大出力電圧でみれば球アンプはずっと大きくなる。
ロードラインを引いてみれば、この差は一目瞭然です。負荷が倍になれば、最大電圧がはっきりと増える。
普通は、定格インピーダンスで最大出力が取れるようにロードラインを引くのでこうなるのです。
最大電圧が増えても出力が増える訳じゃないけど、トランジスタと比較すれば、増えたように見える。
OTLだとそれ程でもない(と言うか設計次第)が、出力トランス付きでは顕著。特に三極出力管ならもの凄く違う。それだけじゃない。出力トランスの損失も変わるのです。
トランスの損失には銅損と鉄損の2種類がある。このうち定損失と言われているもの、つまり銅損が大きく変わってくるのです。これは、コイルの持つ直流抵抗分による損失ですから、電流値によって電圧損失はもの凄く違う。トランスによっても違うが、‘かつ’の使うような安物だと、トランスの一次側で3W近くあった出力が、二次側では2Wを下回ってしまうんだな。多分、発熱も減るだろうから、連続最大出力ではさらに変わるんじゃ無かろうか?
帯域が狭い事、つまり可聴帯域外のパワーが小さいことも有利な条件ではあります。
だって、可聴帯域外で出力したって聞こえないんだから(^^;)。その分必要な帯域におけるパワーを出せるでしょう。
だけど、これは本当に微々たるもの。歪みにしても、それが直接パワーとして十分計測できる程じゃないでしょう。ただ、歪みに関して言えば、歪んだ音を大きな音であると人間は錯覚する可能性はあるかも知れない。
実験してみなければ何とも言えないですが、‘かつ’は昔、電子楽器の研究開発の仕事をしていた事があります。その時に人間の聴覚特性に関する研究論文をたくさん読んだし、また自分でも試してみた。その経験から言って、大出力時の歪みを大きい音圧として感じるという可能性は、十分あるとは思います。
これはねー。私の考えとしては、そんなに問題にならないと思える。10もあれば必要にして十分以上でしょう。
何故なら、スピーカーにはネットワークというものがあるから。DFが問題になる帯域、つまりウーハーでは、一般的には直列にインダクターが入る。その等価直列抵抗、即ちコイルの直流抵抗分がかなりあるのだ。磁気歪みがどうこうなんてのたもうて、空心コイルなんか使えば覿面に大きくなる。
すると、トランジスタなら100以上あるのが普通だけど、そんなの何の影響も無い事になります。さらに、周波数が上がるにつれて、勿論インダクタンスによるインピーダンスの上昇がある。
インピーダンスが零になるのは、実はDCなんだな。勿論、L分で電力の損失は無いのだけども。インピーダンスというのは、複素量であって、L分は jωL で表される。その絶対値がいくら有るかを、よく何Ωです、なんて言い方をして居るんです。所で、問題はスピーカーだってL分が支配的なのだということ。更に高域では、スピーカーコードのインダクタンスが効いてくるし、第一、アッテネータがトウィーターに入ってる。
そう考えると、理論的に言えばアンプの内部抵抗はスピーカーのインピーダンスの1/10以下にする事に、大きな意味は無いんじゃないかと思えます。
フルレンジを使ったバックローディング・ホーン(長岡式なんか)とか、マルチアンプを使ってる人は、低域のみに関して言えば意味があるかも知れない。どっちにしても、私には関係ない世界だ(^^;)。
昔、長岡式バックロードを3回ぐらい造ったけど、あの中域での歪みの多さにはどうしても我慢出来なかった。
私個人の趣味としては、コーン型やドーム型のトウィーターやフルレンジは、聞きづらい。
ホーン/ドライバーのトウィーターとコーン型ウーハーの2wayが一番、聞き易く感じます。きっと、同じ事を言うのにも、「私自ら演奏した経験と、プロオーディオの設計経験から言って、コーン型やドーム型のスピーカーに生の音を求めるのは無理がある。」
な〜んて事を言えば、アマチュアにはウケるんでしょうなー(^^;)。でも、そんなタコな事を言う気は毛頭ありません。大体、人間はある音に慣れる傾向がある。つまり、あるスピーカーの音をずっと聞いていると、それがよい音である、或いは生に近いと錯覚するんだな。逆に生演奏を聴いても、生の音から、無意識にそれに近い部分を引っぱり出して聞いてるんじゃないかと思う。
そういう装置って有るモンです。私自身の経験では、Philipsのスタジオモニター8がそうだった。(実はその音から抜け出すのに何年かかかった^^;;)
他に聴いた範囲では、Quadのアンプなんかそんな何かを感じさせる。金田式アンプもそうじゃないかと思えるフシがある。どれも、私が聴いた限りでは、わりに特殊な音がする所が有る(と言ったら語弊があるか)、個性的な部分があるんだけど、ある種の魅力がそう感じさせるんだと思う。
ま、趣味と割り切ることも大切だと言うことです。