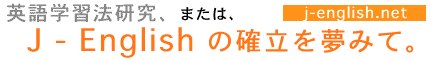
| 仮定法 | |
| 講義トップへ戻る 元の英文へ戻る 次の英文へ 講義の学習の仕方 英文法則の全体像 講義の内容について質問 |
Under the law, had the fathers stepped forward before birth, the children would have been deemed Japanese. 上の英文には、「副-サイン節」の倒置の形が含まれています。元の形に戻すと、 if the fathers had stepped forward before birth という形です。この中のV(動詞)の部分を見ると、had steppedという過去完了形の形になっていますね。完了形の形は「背景表現」なので、過去完了形は「過去のある時点で背負っていた以前の背景」を表すのが基本です。しかし、この部分で使われている過去完了形は、その用法ではありません。この用法を今回は学習しましょう。 動詞の時制変化に関しては、過去の動作を表す場合は過去形、現在の状態を表す場合は現在形を使う、といったことは簡単にわかりますね。ただ、それでは、現実に起きていない動作を表す場合は、どの形を使えばよいのでしょうか。 現実に起きていないのですから、時制を判断する手段がありませんよね。このような場合は、仮定法という特殊なルールに従って動詞の時制を判断します。まず、現在の事実に反する状況を仮定する場合は、仮定法のルールによって過去形を使います。もちろん、事実と違うことで実際には起きていないことなので、過去形の本来の用法とは違いますが、仮定法のルールによって過去形で現在の事実とは違うことを表すということです。たとえば、 If I were you, という「副-サイン節」を考えてみましょう。「もし私があなたなら」という意味ですが、「私があなたである」ということは実際には起こりえないことなので、それを表す動詞の時制は判断できませんね。現在でも過去でも未来でもあり得ませんからね。このような倍は、仮定法のルールに従って時制を判断します。「現在の事実に反することを仮定する場合は、過去形を使う」というルールです。そのルールに従って、ここはwereという過去形になっているわけです(普通に考えればwasですが、仮定法ではwasの代わりにwereを使います)。この形を「仮定法過去」と呼びます。 そしてもう1つ。「過去の事実に反することを仮定する場合は、過去完了形を使う」というルールがあります。ここで過去完了形が出てきました。 if the fathers had stepped forward before birth ということは、この部分は「過去の事実に反すること」を仮定しているということがわかります。「もし、その父親たちが出生前に申し出ていたなら」となります。つまり、事実としては、過去のその時点で申し出なかったわけですね。申し出なかったのですから、その動作の時制が判断できないので、仮定法のルールによって過去完了形を使っているということです。こちらは「仮定法過去完了」と呼びます。 では、もう一度、今回の英文を見てみましょう。 Under the law, had the fathers stepped forward before birth, the children would have been deemed Japanese. 「その法律の下では、もしその父親たちが出生前に申し出ていたなら」という部分までわかりました。その後の部分を見てみると、V(動詞)は「助動詞+完了形」の形になっていますね。これは、以前学習したように「過去に関する主張」を表す形です。ただ、助動詞がwillではなくwouldとなっていることに注意してください。これは、「もし〜なら」というように何らかの仮定を元にして主張をする場合、その主張を弱めるために助動詞を過去形の形に変えます。したがって「その子供たちは、日本人として考えられただろう」という意味になります。 では、仮定法過去と仮定法過去完了の形を練習しておきましょう。 <例文1> If there was a general election now, the DPJ would be stronger than the LDP.
*general election<名詞>総選挙
「副-サイン節」+イメージ2+「副-サイン節」です。 1つ目の「副-サイン節」の中のV(動詞)を見てみると、過去形になっていますね。この部分の最後にはnowとついているので、おかしいですね。これは、仮定法過去が使われているということです。つまり、事実としては、今、総選挙はないが、「もし、今、総選挙があったなら」という仮定をしているわけです。 そして、イメージ2の部分は、助動詞を使って主張をしていますが、その助動詞がwouldとなっています。これは、仮定を元にして主張をしているからですね。
If there was a general election now, the DPJ would be stronger than the LDP. 「もし、今、総選挙があったなら、民主党は、自民党よりも強いであろう。」 <例文2> The death toll almost certainly would have been much higher had the quakes struck a major city.
*death toll<名詞>死者数
イメージ2+「副-サイン節」です。 「副-サイン節」の部分は倒置の形になっています。仮定法が使われている「副-サイン節」では、このようにifを省略して内部を疑問文と同じ倒置の形にすることがよくあります。元の形に戻すと、 if the quakes had struck a major city こうなります。V(動詞)が過去完了形になっていますね。これは、仮定法過去完了の形ですから、「過去の事実に反すること」を仮定しているということです。つまり、事実としては、地震は大都市を襲わなかったが、「もし、その地震が大都市を襲っていたら」という仮定をしているわけです。 そして、イメージ2の部分のV(動詞)は、助動詞+完了形の形になっているので、「過去に関する主張」をしていることがわかります。また、助動詞はwouldとなっていて、仮定を元にした主張であることがわかります。
The death toll almost certainly would have been much higher had the quakes struck a major city. 「もしその地震が大都市を襲っていたら、死者数は、ほぼ確実に、ずっと多くなっていたであろう。」 <例文3> The fraud might have been prevented had the entities designated to inspect building strength required Aneha to submit the necessary documents.
*fraud<名詞>詐欺
これはちょっと構造が難しいですね。「副-サイン節」は倒置の形になっています。よく注意してみてくださいね。元に戻すと、 if the entities designated to inspect building strength had required Aneha to submit the necessary documents こうなります。内部構造を確認すると、
イメージ5です。名詞Aに「形容-分詞句」の修飾がついているので注意してくださいね。その内部構造は、
イメージ2を利用しています。 さて、この「副-サイン節」の中のV(動詞)は、過去完了形になっています。つまり、仮定法過去完了の形ですから、「過去の事実に反すること」を仮定しているということです。事実としては、要求しなかったが、「もし、要求していたら」ということです。 そして、イメージ1の部分のV(動詞)は、助動詞+完了形の形になっています。mayではなくmightになっているので、仮定を元にした過去に関する主張であることがわかりますね。
The fraud might have been prevented had the entities designated to inspect building strength required Aneha to submit the necessary documents. 「もし、建物の強度を検査するように指定された団体がAnehaに必要書類を提出するように要求していたなら、その詐欺は防げたかもしれない。」 |