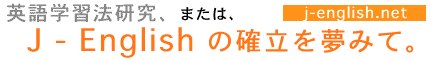
| 助動詞+完了形 | |
| 講義トップへ戻る 元の英文へ戻る 次の英文へ 講義の学習の仕方 英文法則の全体像 講義の内容について質問 |
The Diet, however, approved a stopgap bill to maintain until the end of May various other special tax measures that would have expired Monday, the final day of fiscal 2007. 上の英文の中に、would have expiredという表現がありますね。ここでは、この「助動詞+完了形」という表現についてまとめてみます。 まず、助動詞が「話者の主張」を表すことを押さえましょう。たとえば、 He goes to school. 「彼は、学校へ通っている。」という英文は、事実を表していますが、これに助動詞が加わると、 He may go to school. 「彼は、学校へ通っているかもしれない。」というように、事実を表すのではなく、「話者の主張」を表す表現になります。事実として「通っている」のではなく、「〜かもしれない」と発言者が頭の中で考えているわけですね。 このことは、基本的にすべての助動詞に共通の性質で、 He can go to school.「彼は、学校に通うことができる。」 He should go to school.「彼は、学校へ通うべきである。」 He must go to school.「彼は、学校へ通わなければならない。」 すべて、事実ではなく「話者の主張」を表す表現です。canは「可能性の主張」、mayは「蓋然性(確率)の主張」、shouldは「妥当性の主張」、mustは「必然性の主張」を表します。 このように、「助動詞+動詞の原形」の形の場合は、「現在のことに関する話者の主張」を表す形です。これに対して、「助動詞+動詞の完了形」の形の場合は、「過去のことに関する話者の主張」を表す形になります。たとえば、 He can have gone to school. というように「助動詞+完了形」の形になれば、「過去に関する主張」を表し、なおかつcanなので「可能性の主張」ですから、「彼は、学校へ通っていた可能性がある。」となります。同様に、 He may have gone to school.「彼は、学校へ通っていたかもしれない。」 He should have gone to school.「彼は、学校へ通うべきだった。」 He must have gone to school.「彼は、学校へ通っていたに違いない。」 というように、「助動詞+完了形」は、すべて「過去に関する主張」を表すことになります。 特に、最後のmust have goneは、「学校へ通わなければならなかった」と勘違いする人が多いので注意してください。違いがわかりますか?「通わなければならなかった」というのは、「過去の義務」という事実の表現なので、助動詞を使う表現ではありません。had to goという表現を使います。 have toは「〜しなければならない」という意味で、mustとよく似ていますが、厳密に言えば、助動詞ではありません。mustは、「話者の主張」という主観的な表現ですが、have toは、「これから〜する状況を抱えている」という客観的な表現です。したがって、「通わなければならなかった」という「過去の義務」を表す場合は、had to goを使うわけですね。 さて、「助動詞+動詞の原形」と「助動詞+完了形」の表す意味を見てきました。ただ、今回の英文では、would have expiredというように、「助動詞+完了形」なのですが、助動詞がwouldとなっていますね。willの場合とwouldの場合はどのように違うのでしょうか?それを見てみましょう。 willという助動詞に対し、wouldはその過去形の形です。ただし、助動詞は「話者の主張」を表すので、過去形だからといって過去のことを表すわけではありません。willに対しwould, canに対しcould, mayに対しmightを使う場合は、「ある仮定を前提とした主張」を表します。つまり、「もし〜なら」という仮定があっての主張というわけです。 さらに、この「もし〜なら」という仮定は、はっきりと表現されている場合と、表現されていない場合があります。はっきり表現されている場合は、特に問題はないのですが、表現されていない場合は、それを読み取らなければなりません。ただ、誰でもわかるから表現されていないわけで、読み取ること自体はそれほど難しいことではありません。 たとえば、今回の英文を見てみましょう。 The Diet approved a stopgap bill to maintain until the end of May various other special tax measures that would have expired Monday. このwould have expiredという表現は、「助動詞+完了形」で、さらに助動詞がwouldになっていますね。つまり、仮定を前提として、過去に関する主張をしているわけです。 ただ、この英文の場合、その「仮定」がはっきりと表現されていませんので、それを補う必要があります。それを頭の中に入れておいて、この英文を訳してみましょう。 「国会は、月曜日に期限切れになったであろう様々な他の特別税措置を、5月末まで維持する一時しのぎの法案を承認した。」 これだけの情報があれば、would have expiredという表現が、「もし国会が一時しのぎの法案を承認しなければ、月曜に期限切れになったであろう」という意味であることがわかりますね。これが、「助動詞の過去形+完了形」という形が表す意味です。 では、1つだけ例文を見てみましょう。 <例文1> Narita airport will continue to lack a crosswinds runway, which would have been 3,200 meters long under the original plan. *continue<動詞3>続ける
イメージ3です。名詞Bは「名-to原形句」になっていて、その中の名詞には、非限定の「形容-代用詞節」の修飾がついています。その内部構造は、
イメージ2+「副-前置詞句」です。このV(動詞)の部分は、「助動詞+完了形」になっているので「過去に関する主張」を表していることがわかります。そして、助動詞がwouldなので、「仮定」を前提として主張しているのですが、その「仮定」が表現されていません。したがって、文脈から読み取る必要がありますね。すると、「もし元々の計画通りになっていれば、3200メートルになっていたであろう」という意味が読み取れます。
Narita airport will continue to lack a crosswinds runway, which would have been 3,200 meters long under the original plan. 「成田空港は、引き続き、元々の計画では3200メートルの長さになっていたであろう横風滑走路を欠いた状態が続くであろう。」 |