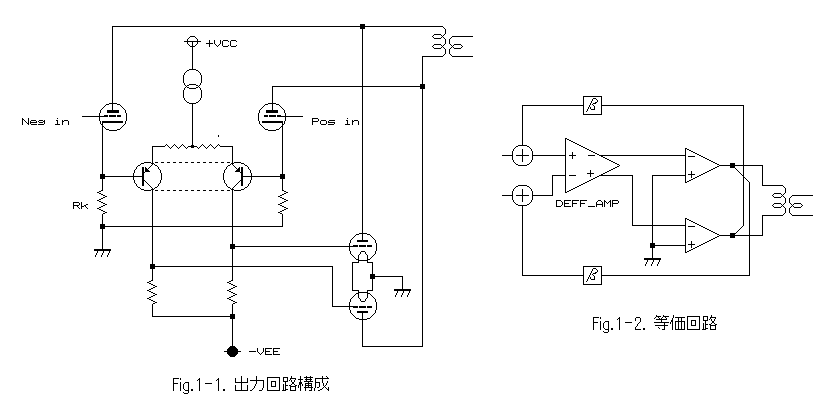
RCA��2A3(JAN CRC-2A3)�̃y�A�`���[�u(�X�e���I��)�ƃ^���S�̓d���g�����X�A�d���`���[�N�ALUX�̏o�̓g�����X�A12AT7��12BH7��S�ă^�_�ł�������̂ŁA���Ƃ��Ă͏��߂Ă̒��M�O�ɊǃA���v����邱�Ƃɂ��܂����B
�Ȃ�Œ��M�ǂ����߂Ă��Ƃ����ƁA�P�ɒl�i�������Ĕ����Ȃ�����B�i^^;/
�ŋ߂ł����������V�A���̋��Ȃ��邵�A�������̕i�����ǂ��Ȃ��Ă܂����ǁA�̂͒������Ȃg����㕨����Ȃ��������A���V�A�����M�ǂ͓����Ė��������̂ŁA���ǎg���Ȃ������̂ł��B
�܊p���̂Ȃ�A�����ʔ����b�͖������Ǝv���Ē��ׂĂ݂�ƁA�ŋ߂͍����o�͂����s���Ă�悤�ł��B
�����ŁA���̍l�������A�����W���āA���Ȃ�̉��߂ł̉�H�����삵�Ă݂܂����B
�P�@DEPP�̖��_�ƑS�i�����\��
DEPP (Double Ended Push Pull) �̖��Ƃ͉����H���Ȃ��Ƃ��萫�I�ɍl�������́ASE
(�V���O��)�ɑ���DEPP�����_�Ƃ����̂͌��������܂���B
�ɂ��ւ�炸�A�D���Ƃɂ̓V���O�������Ă͂₳��A�H��SE�͑f�����Ƃ��Y��ȉ����Ƃ������܂��B
����Ɋ֘A���āA�ŋ߁A���������őS�i������H����肴������Ă���悤�ł��B�J�̕]���Ƃ��ẮASE�ɋ߂��Ƃ̈ӌ��������悤�ł��B
�v����ɁA���̕����ŖڐV�����͍̂����o�͒i�ł����A���ʂ�DEPP�ɑ��Ăǂ̂悤�ȓ����������l���Ă݂܂��傤�B
�悸�A�����b�g�Ƃ��̉\���Ƃ��Ă�
1. PP�������g�����X�̈ꎟ���d�������ɂ��Ȃ��B�i�ł́A�����ɉ��̃����b�g������̂��H�j
2. �d�����猩�āA�قڊ��S�Ȓ�d�����ׂł���B���ׁ̈A�d���ϓ���b�v���ɑ��ċɂ߂ċ����B
3. ���R�����A�o�C�A�X�d���͂قڊ��S�Ɉ��肷��B�o�͒i�ł̃h���t�g�͌�������B
���炩�ȃf�����b�g�Ƃ��Ă�
4. �o�͂��傫�����̘c�݂�������B
5. A���ɂ����ł��Ȃ��B�܂��A���ϓd�������������Ȃ��̂ŁA���ʂ�A��PP�����ő�o�͂��������Ȃ�B
6. ����̋������ƁA�I�[�g�}�`�b�N��(�H)���������B
7. �o�͂�rp�i���̓�����R�j��2�{�ɑ�����B
�Ō��7.�͗��R������ɂ��������m��܂���B����̃J�\�[�h�̏o�̓C���s�[�_���X����������̃J�\�[�h����݂��d���A�҂ɂȂ邩��ł��B���ŏ����ƁA
rp = ��/gm�@���@Rk = 1/gm �́A
rp' = rp + Rk�� = rp + ��/gm = 2rp
�ƂȂ�܂����B
�܂��A���ϓd�����������Ȃ��ƌ������Ƃ́AA�����ȃo�C�A�XPP�Ɠ����悤�ɁA��o�͎��ɂ͘c�݂ł��s���ɂȂ�͂��ł��B
���Ă̒ʂ�A�I�i�̍������͖��炩�ɕ��������ʂł͕s���ł��B�����Ɍ���ɂ��������ł̃����b�g���ۗ����܂��B
�������l���Ă݂�ASE�����Ė��炩�ɂ���������ŕs���A��������o�͂�]�߂R�X�g�ł��s���Ȃ̂ɁA�ˑR�Ƃ��Ĉꕔ�̍D���Ƃ�琔��҂��̐S�𑨂���̂́A���Ȃ����m�X�^���W�[����Ƃ������܂��܂��B
�Ƃ���Ȃ�A���ۂɉ����I�ȃ����b�g�ƂȂ��Ă���̂́i��������Ƃ���Ȃ�j���ł��傤�H
3. �̉\���͒Ⴂ�ł��傤�B����Ȃ�A�u�Œ�o�C�A�X�����A���ȃo�C�A�X�̕����ǂ��v�ƌ����ӌ����o�Ă��Ă��ǂ������ł����A�t�̈ӌ��������ɂ���A����Șb�͕�������������܂���B
�����b�g�� 1.�� 2.�ł��傤���A����͘A���������ł�����ɂ�ł��܂��B�d���𒆐��_�Ŏg��DEPP�ł́A�o�̓C���s�[�_���X�[���̓d�����A100%���S��PP�o�����X�����������Ȃ�����́A���_���h��邩��ł��B
�ł͂�����́A�g�����X�̈ꎟ�d�������ɔ������Ƃ͉��ł��傤�H
���������A�g�����X�ɂ��d���������A�{���ɉ����I�ȃf�����b�g�ƂȂ蓾��̂��́A�c�_�̗]�n�̂��鏊�ł����A�ꉞ���ꂪ�����ɗ^����e�����傫���ƌ�������̌��ɘb������ƁA���S��PP���t���Ƃ鎖���A���S�ȓd������������ł���̂͊ԈႢ�̂Ȃ����ł��B
�g�`�������g�����X�̈ꎟ�d�������ɗ����Ă���̂�����������肾�Ƃ̈ӌ�������悤�ł����A�ł͉��̂��ꂪ���Ȃ̂��A�Ƃ̖��m�ȓ����́A�s�K�ɂ��Ė���������������܂���B
�ʏ��DEPP�ł͑o��������̍����ɔ����āA�ꎟ���ɂ̓R�������[�h�d��������܂����A�����o�͂ł͂��ꂪ����܂���B
�������A���ۖ��A�����d��������邱�Ǝ��̂����ł���Ƃ����͖̂����Ǝv���̂ł��B
�����{���ɂ��ꂪ���Ȃ�A���M�ǂ�AC�_�̉��͑ʖڂł��B�d��AC�̎��g���ŃR�������[�h�d��������܂�����B
������A�������ꂪ���R�ł���Ȃ�A2A3���300B���s�������Ahundred watter
�ƌĂ��ނ̑��M��(845����1000V��)�Ɏ����ẮAPP�ł����Ă������_���邵������܂���B
���ł���Ȏ���ˑR�����o���̂��Ƃ����ƁA�R�����d����������(??)SE�p�̏o�̓g�����X���Q�g����PP�A���v�̐���L�����G���ɏo�Ă����̂ŁB
�Q�@�ϕ��������Ɣ���������
�����ω������ƌ������Ƃ́A�g�`�̕ω��ł��B����͊ԈႢ����܂���A���炩�̘c�݂ł��傤�B
���g�������̗ǔۂɂ��c�݁A�����U���c�݂ƈʑ��c�݂Ɋւ��Ă�DEPP�̕���SE���y���ɗD��Ă��܂��B
�����g�c�݂Ɋւ��Ă���Ηʂł�DEPP���D��܂����A3�����g��SE����������X���ɂ���܂��B�������A����͍�������������ƌ����ėǂ��Ȃ�Ⴀ��܂���B
�Ƃ���ŁA���o�ł̉�H�A�܂�r�f�I��H�ɉ����钼�����Œʏ���ɂ���̂́ADG/DP�ł��B�e�XDifferential
Gain / Differential Phase �̗��ł��B
�ϕ��������ł͂Ȃ����������������ɂ����̂ł��B
���݂ɁA�����������͉����p�� D/A, A/D �R���o�[�^�ɂ����Ă��A���̒P���������߂�d�v�Ȏړx�ł��B�̂�R-2R���_�[��R�ɂ�钀����r�����̎���̍����@�ł́A��x�����͂�p����MSB�̒������s���Ă��܂������A����͔��������������コ����ׂŁA���̒����ɂ���Đϕ��������͈����Ȃ�ꍇ���炠��܂��B����������������D/A�Ŏc���̑������y���ƁA�c���������m�C�Y������ɕ������܂��B�����l����ɁA���o�ɂ����Ă����ɂ��ׂ��͂�����ł��낤�Ǝv���܂��B�����āA�̂̓r�f�I��H�o�͂ł�SEPP�̃t�H���A�����܂�p���܂���ł����B�i���邱�Ƃ͂���܂������ǂˁB�j
���ʂ͑�d���𗬂���SE�t�H���A�ł����BDG/DP�ɑ���z���̂��߂ł��B
���ʂ�DEPP�ł����Ă��A�o�͊ǂ����S�ɑ����Ă��āA�g�����X�̈ꎟ�d��������100%�ŁA�d���d�ʂ����S�Ɉ��Ȃ�(�܂�S���g���ш�ŏo�̓C���s�[�_���X�������ł���قǏ��������)�A�������������ǂ��Ȃ锤�ł����A����͕s�\�Șb�ł��B
�o�͒i�̍������́A���̉e�����ł��郌�x���܂Œǂ����ޕ��@�̈�ł����A����͗͋Ɓi������킴�j�ł��B
��H���ȒP�ɂȂ邱�Ƃ͑傫�ȃ����b�g�ŁA���₷���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł����A���̓����ʂŌ����ΑS�Ă������̂ł�����B
�R�@���O�Ɋǐڑ�MX
�����ōl������̂��ANFB�ł��B�����܂��A�Ǝv���邩���m��܂���B�ł��A���ꂪ��ԊȒP�ł��B
���ہA�ŋ߂̓r�f�I��H�ł��\����NFB�ł����Ă����Ȗ���������������ł��B(�ŋ߂�OP�A���v�ɂ͓d���A�҂�40MHz���M�������e�B�[������̂܂ł���܂��B�m�[�g���A�҂ł́A����40MHz��IF�i�ɁAOP�A���v��10dB�̃p���[�Q�C������������Ƃ��炠��܂��B)
�ŁA�l�����̂��}1-1�Ɏ�����H�ł��B������H��}1-2�Ɏ����܂��B
�e�o�͒[����A���O���i���h�L�j�Ńv���[�g�A�҂��|���A�����̂̍����A���v�ō������Ă��܂��B
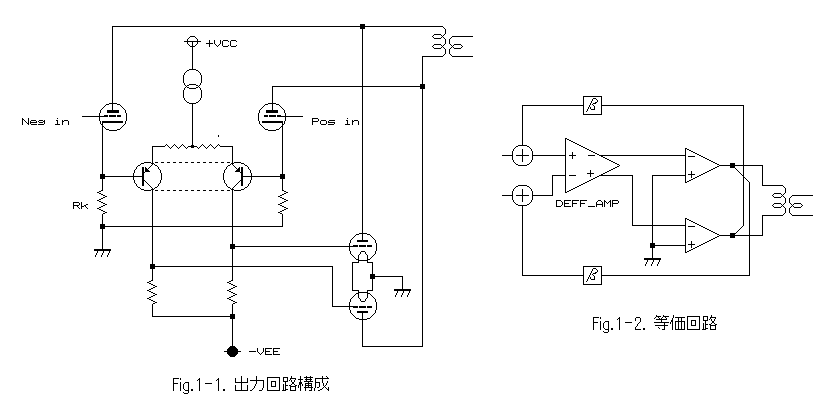
�����̂̍����A���v��CMRR�́A��d�����ŋ��ʃG�~�b�^���60dB�ȏ�͊ȒP�ɃN���A���܂��B�{�@�̂悤�ɁA�������|���̐[���A�҂�������Aꡂ��ɂɑ傫���ł��B�i����͑������Ⴀ��܂���B���ۖ��Ƃ��āA������Ԃł͂��Ȃ����B�j
Fig.1-2 �̓�����H�̃��́A�^��ǂ̃v���[�g��R���ƃJ�\�[�h��R�̔�ŁA�irp+Rk��ʁj/Rk���ʂł�����A���[�v�Q�C���͂قڃʂł��B�������́A�T����Rc/Re�(2A3�̃�)���炢�ł��B
(�����ɂ�2A3��rp�ƃg�����X�̈ꎟ�C���s�[�_���X�̕���l�~2A3��gm�ł�����A�ׂ������Ƃ�������A������͈͂�AB������͈͂ł͋A�җ����Ⴂ�܂����A�吨�ɉe���͂���܂���B)
���A���O�Ɋǐڑ��̊�{�ƂȂ�l�����������ɏ����Ă���܂��B
���[�J����NFB�ʂ͐^��lj�H�Ƃ��Ă͋ɂ߂đ傫���A34dB�ɂ��B���܂��B�����Ƒ傫�����ł��܂����ADC���萫���l����ƁA���̕ӂ��Ó��ł��傤�B���܂�傫�ȃI�[�v���Q�C���̓h���t�g�����ɂȂ�܂��B
����ɂ��A����������̍����o�̓A���v�̂悤�ɐU�镑���̂ł��B�]���āA���_�͉��������n�Y����Ȃ�ł����A����Ă݂Ȃ�������܂���B
���_�́A���炩�ɕ��i�_����������̂ƁA�h���t�g���o�邱�ƁB
����ɁA���̂܂܂ł̓|�[�����ڋ߂��邵�A�A�Ґ^��ǂ̘c�݂����ɂȂ�̂ŁADC�T�[�{�ƃG�~�t�H���������܂��B
�����������P���邽�߂ɁA���O��V1�̎�@��p���Ă��܂��B�����A�o�͐M���d�ʂ��������قNjA�Ґ^��ǂ̃v���[�g�d����������l�ȃ��[�h���C���ɂ��܂��B���ɂ��̊T�O�}�������܂��B
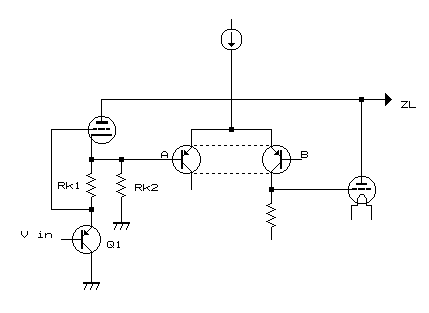
A-B�ԃx�[�X�d���͐[��NFB�Ŗw�Ǔ����Ȃ�(�C�}�W�i���V���[�g)�̂ŁAVin���㏸����Q1�̃G�~�b�^���㏸����ƁARk1�ɗ����d���͌������܂��BGND-K�Ԃ̒�RRk2�ɂ́A�M���Ɋւ�炸���d��������܂��B
����ŁA���ג����͌X�������ł��^���ł����R�Ɉ������Ƃ��o���܂��B�v���[�g�d��(�A�ғd��)�������Ƃ��قǁA�A�Ґ^��ǂ̃J�\�[�h�d���͑����܂�����A���̕��͏I�i�̒��M��(�}���ɂȂ����]��)�ɃR�������[�h�ł��������`�œd��������܂��B
�������ŁA��╡�G(?)�ȉ�H�ɂȂ�܂����B
���G�������̂́A����������2A3���u���Ŏg���킯�ɂ͂����܂���A���i�ɎO�Ɋǂ��g�����ƂɍS�������ɂ��W������܂��B���i��FET�Ȃ�A���O��V1�Ǝ����悤�Ȑڑ����l����Ύ�����܂�����ˁB
�ł�����ȏ�ɁA�c�O�Ȃ���A���̕n���ȓ��ł́A���i�O�Ɋǂɂ��Ă���ȏ�͎v�����Ȃ������Ƃ������ł��B
��Ǝv�����A�����ƃV���v���ł��������O���[�g�ȉ�H���l���Ă���ĉ������B(^^;;)
�A�Ҋǂ̓���Ƃ����[�h���C���͒��O��V1��V2�̒��Ԃł����A��H��VX�ɂ����Ă��܂��B�l���悤�ɂ���ẮA�_�[�����g���Ƃ������邩���B���O�Ɋǐڑ����h�L�̃^�X�L�|���A�Ŗ��Â��Ē��O��MX�B
�S�@�S�̂̉�H
�v�����A���v���̉�H��}2�Ɏ����܂��B
����́A�����ڂ�����H�̐v�ɂ��ď����܂��B���A��H�}���̓d���͎����l�ł��B
(�A���A���i�`�h���C�u�i�d���d���͌�̒����ŕύX���Ă��܂��B����ēd���͎Q�l���x�ɂ��ĉ������B)
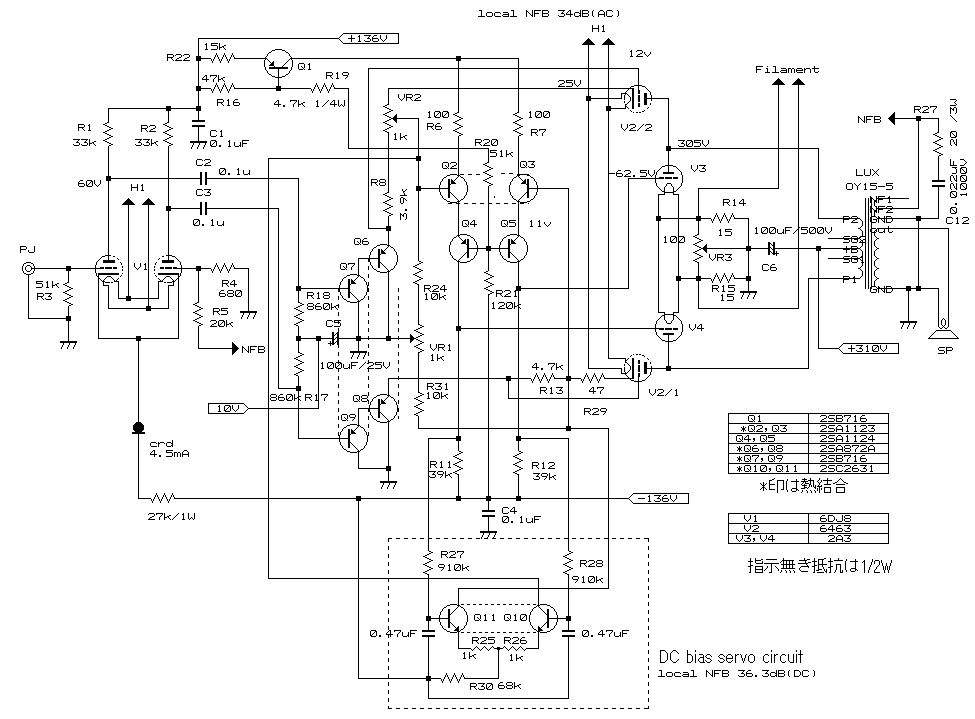
�S�|�@�@���i
�܊p�����12AT7�ł����Q�C�����傫�����邵�A�c�݂������̂ŁA�ړI�ɔ�����킯�Ŏg���܂���B
�ŁA���i��6DJ8�ɂ���d���t���̍����A���v�ł��B
�����o�����X���l�����āA�g�����X��NFB����������A�҂��|���Ă��܂��B
����_�̑I��͗����ƒ������ƕK�v�ȏo�̓��x������ǂ������ʂł��B
�I�[�o�[�I�[���̕��A�҂��y���������̂́A���i�̍������t�iAC�o�����X�j�����P���悤�Ƃ����ژ_���ł��B�����Ă�������͏\���ł��傤�B
�S�|�A�@�h���C�u�i�`�I�i
�ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɁA�h���C�u�i�ƏI�i����̂ɂȂ��ē��삵�܂��B
�h���C�u���g�����W�X�^�ɂ��āA�\���ȗ������҂���NFB�ʂ𑝂₷�Ƌ��ɁA�I�i�Ƃ̒��������\�ɂ��Ă��܂��B
�����2A3�Œ�o�C�A�X�Ŗ��ɂȂ�A�ႢRg�͈ꋓ�ɕЂ��t���܂��B(�Œ�o�C�A�X�ł�50k���ȉ��B����ȏゾ�ƃO���b�h�d���ɂ��M�\���̊댯������܂��B)
���́A���߂͑S�i�������l��������ł����ǁA�v�Z���������Œ��߂܂����B
��ɖ����ł��ˁA���Ȃ�[��DC�T�[�{�ł������Ȃ���}�g���ɓ��삵�܂���B�I�i��DC������AC������1/20�ȉ��ł�����A�ʂɃT�[�{�A���v�ŃQ�C�����҂��Ȃ���A�A�җʂ�����܂���B
�₽���H�����G��������ɂ́A�i�ԃR���f���T���Ȃ��Ȃ邾���ł��B������DC�o�C�A�X�d���������Ƌt���œ����ɂȂ�l�ɁA�ʂ̃T�[�{���K�v�ŁA�n���݂����Ɏv���Ă����̂Ŏ~�߂܂����B
�A�Ҋǂ̑I��͏d�v�ȕ����ł����A���M����6463��I�����܂����B���������ǂ���rp�����Ə������A���ψ��ł��B
���ɑψ��́AVapk��Vao��������660V�ł�����A���������p�r�ɂ͍œK�ƌ����܂��B
�������12BH7A�͂��܂�ɂ��������������B
6DJ8�t�@�~���[��5687�݂����ȍ�gm�ǂ��A�����g���Ȃ��ł��傤�B10mS�ȏ�����鍂gm�ǂ́A�o�C�A�X�d���̂�����傫���ł�����A2�i�ڂ�DC���͓d�ʂ�����Đv�ł��܂���B
������������Ƌ��ɁA6463�̋A�җe�ʂ̉e����}���邽�߂�PNP�̃G�~�t�H�������Ă���܂����A�G�~�t�H������ꂽ���ۂ̉�H�̓���_�ƃ��[�h���C�������ɐ}�����܂��B
�ʏ�̕��א��Ƃ͌X�����t�ɂȂ�܂�����A���̕��o�͊ǂ̕��ׂ͂ق�̏����d���Ȃ�܂��B
���̑��蒼�����͋��ٓI�ɗǂ��Ȃ��Ă��܂��B�}�̓_���̓�=21�ŋ���Ă܂����A50�`450V���A�قڊ��S�ɑ��������ł��B
�����̃o�C�A�X�d���Ɛv�l�́A���ɗǂ���v���Ă��܂��B
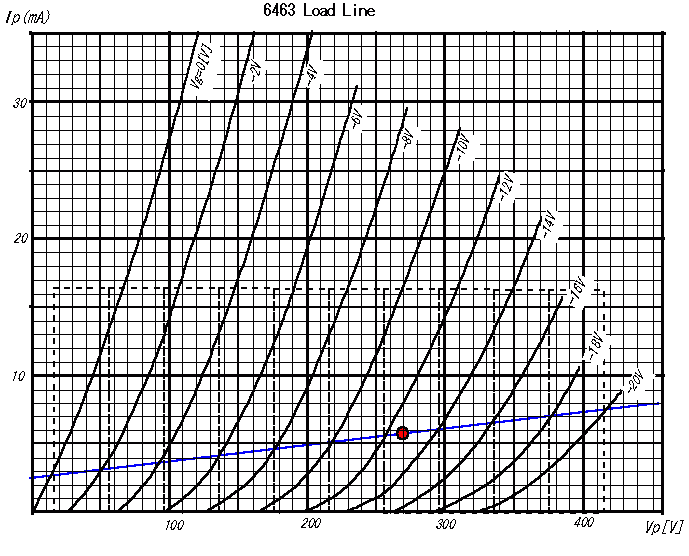
���O�Ɋǐڑ��̗�ɘR�ꂸ�A�o�͂̓����͂��̃��[�h���C���̒ʂ�̑������ɂȂ�܂��B���ꂪPP�œ��삷��킯�ł��B
���O���̋A�҂ɂ��2A3�v���[�g�ł̏o�̓C���s�[�_���X�́A�������͂ɑ��Ă�12�����炢�ł�����A���x��̐}�̓_���̂悤�ȓ����ł��B
���̓_���������ɐL����5k��PP�̃��[�h���C�������������(300V�t�߂œd��0�A0V��240mA)���������̏o�͕��א��ł��B
���ŁA2000�N11������MJ�ɍ��쎁��2A3�̃p��PP�̋L���������Ă��܂��B�Ȃ�ƁA���i7DJ8�A2�i�ڂ�6463���̗p���Ă��܂��B
���Ɠ����l�ȑI���ɁA�т�����I
�����7044�J�\�t�H���������Ă��܂����A7044�͎��̂悭�g��5687�����̍��M���ǂ��������ɂ��Ă��A6463�́A���͓K�ȋ���T���܂��������ʂ����ɁA�ȂG���Ő�ɔ��\�����Ɖ��������̂�����܂�(^^;;�B
�G�~�t�H���̓_�[�����g���ɂ��Ă���܂��B�o�C�A�X��R��傫���Ƃ��đO�i�̃Q�C���ቺ��h���ׂł��B
�_�[�����g�������ŁA���̂��炢�̒�R(820k��)�Ńo�C�A�X����A�x�[�X�d���Ŕ�������d����10V�ɂ��B���Ă��܂��܂��B�������AhFE�͉��x�ˑ���������܂�����A���̓d���͉��x�ŕω����܂��B
�_�[�����g���ɂ��邱�ƂŁA�����Ƀ��t�Ȑv�����e���Ă���܂����A�ꉞVbe�ϓ��͏I�i�o�C�A�X��ω�������̂ŁA�����Ƌt����Tr��hFE�𑪒肵�ē����𑵂��A�M�������Ă����܂����BDual-Tr
�Ȃ�A�����ƊȒP�ł��B
2SA872�́AASO�������ł����A�ɂ߂ď����ȓd����ŋ����قǗǍD�ȓ����������܂��B
2SB716�͋ɏ��d����͕s����ł���d����ł̃��j�A���e�B�[�ɗD��AASO�͂����ƍL���ł��B
������2SA872A�|2SB716�̃_�[�����g���ɂȂ��Ă��܂��B
�����́APchMOS-FET�̃\�[�X�t�H���A�͓��͗e�ʂ��傫�����đʖځA��gm J-FET�ł�Vgs�̉��x������6463�̃o�C�A�X�ω����傫�����܂��B
�g�����X�͌Œ�o�C�A�X�ɂ��ւ�炸�T�����ɂȂ��Ă��܂����A�v����ɂ�������g�����X������ł��B
2mA���x�ł����A�Ҋǂ̓d�����o�͊ǂɗ���܂�(�ꎟ���ŃR�����ɂȂ�܂�)�BOY-15�͗y���ɑ�o�͂����e����̂ŁA���Ȃ��ł��傤�B
���ŁA���̃g�����X�͖{���� LUX OY-15-5�Ƃ͈Ⴄ�Ƃ��낪����܂��B
���̂�NFB����������A�����(?)4���[�q��16���[�q������܂���B
(�t���̖��ɏ����ꂽ�z���\�ɂ�4��/16���[�q������A�t��NFB����������܂���B)
�����A���̐̂ɂǂ�����Hi-Fi���[�J�[�����Ђ̃Z�p���[�g�X�e���I(����I)�p�ɍ���������i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����������NFB�����ł�����A���肪�����g�킹�Ē������ɂ��܂��B(���ʁA�o�͒[���炩��������ʑ��������ǂ��Ȃ�܂��B)
�I�i�͐[�����A�҂Ɋ��҂���(?)AB������ɂ��܂��B�ʏ�����o�C�A�X�͋͂��ɐ[�߂̐ݒ�ł��B
���̕��A�h���C�u�̐U���͑傫���Ȃ�̂ŁA���d���̓d���͍����Ȃ�܂��B
�A�Ґ^��ǂ̓d��������̂ŁA�������܂����B
�܂��A���B�d�������߂ł��B
�S�|�B�@�o�C�A�X�E�T�[�{��H���́A�ŏ��͂���A���������̂ł��B
���쌴���͒ʏ��DC�T�[�{�Ƃ͑啪�Ⴄ�̂ŁA�������܂��B
2A3�O���b�h�d�ʂ�Tr�����A���v�̃R���N�^�d�ʂł��B�����A���v�͒�d���Ŕ����Ă��邩��A���̃R���N�^�d�ʂ������Ƌt���œ����ɂȂ�Ηǂ��킯�ł��B
�����ŁATr�����A���v�̃R���N�^����LPF��ʂ���DC�d��������āA�ʂ̍����A���v�ɓ��͂��Ĕ��Α��Ɣ�r���Ă���킯�ł��B
�A�Ҋ�(6463)�̃J�\�[�h�ɋA���Ă��܂����A����͓d�����̋A�҂ł��B
�O���b�h�d�ʂ̓G�~�t�H���ŌŒ肳��Ă��܂����A�J�\�[�h�d�ʂ͂��̎��̓d���Ō��܂�̂ŁA����Vgk���ς��܂��B����ƃJ�\�[�h�ɐڑ����ꂽ�����A���v�̃x�[�X�d�ʂ��ς��A�Ƃ����d�g�݂ł��B
�T�[�{�E�A���v���̂̓Q�C��������܂��A���X���n�C�Q�C���Ȃ̂ł����ŃQ�C�����҂��ł������������˂�̂��I�`�ł��傤�B
�f���ȉ��������ɂȂ锤�ł����A����ł����̎��萔�͏\���ɒႭ�Ȃ��ƕs����v���ɂȂ�܂��B�o�͒i�̎��萔�̗\�z���t���Ȃ�����A�i�ԃJ�b�v�����O���萔�̖�T�{�ƁA�X�^�K���傫�����Ă��܂��B
�S�|�C�@�d����H���̓���Y�܂����̂��A�d�������i�̓d����H�ł��B�K�v�ȓd���ɑ��āA�g�����X�̓��������Ƃ��ẮAAC330V �� AC80V �����Ȃ������̂ŁA�ǂ��g�ݍ��킹�Ă��ʖڂł��B
�����Œ�d���d���̗̍p�ƂȂ�킯�ł����A�Ȃ�Ƃ��g����悤�ɂƁA�l������H�ł��B
�t���[�e�B���O����̃V�����g�d���ƃV���[�Y�d����g�ݍ��킹���A�V�`���̃g���b�L���O�E���M�����[�^�ł��BSSPS�Ɩ��O��t���܂����B
���炢���̂̓d���g�����X�ʼn��Ƃ���낤�Ƃ������ʂł����A�K�v�͔����̕�ƌ�����ł��B
����SSPS��H�̊T�O�}�����}�Q�Ɏ����܂��B
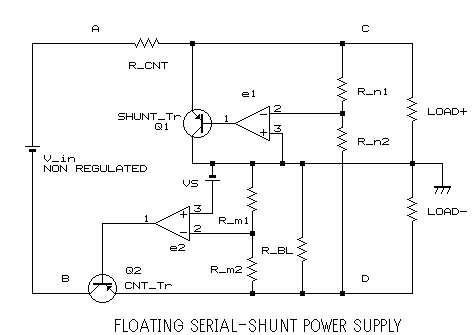 �}2
SSPS circuit
�}2
SSPS circuit
���������������K���d���l���������Ƃ�O��ɂ��Ă���̂ŁA�d���̕�����R_BL�Ńu���[�_�d���𗬂��܂��B�i���ۂɂ̓c�F�i�[�_�C�I�[�h�ւ̓d����5mA������ɑ������܂��B�j
�����̃V�����g�d���̒�R R_CNT �ɂ�����d���iA-C�j�́A�d���������d���l�~��R�l�ɂȂ�܂��B�]���āA�����̃V���[�Y�d����Q2�ɂ́AV_in����o�͓d�� D+C �������������d����������܂��B
��{�I�ɂ́A���ׁi�A���v���j�̓d�������ƕ��Ŗw�Ǔ��������炱���\�ȉ�H�ł����A�����������̓d���l�����������ω����Ă��A�����̃V�����gTr Q1 �ɗ����d�����ω����邾���ŁA�d���̃g�[�^���� AB�Ԃ��猩��Εω����܂���B�����̓d���������������Ƃ���A�t�ɐ����̐���Tr Q2 �̓d���l�͕ς�炸�ɁAR_CNT �ɂ�����d�����ω����܂��B
�܂�A�O�����h�𒆐S�ɂ��āA�V�����U���݂����Ɉꎟ���Ɋ|����d�����ς��킯�ł��B
�A���A��{�I�ɂ͂��̓d����H���l�����āA�A���v�̓d�������i�͐����̓d���ƕ����̓d�����������Ȃ�悤�ɐv���Ă��܂�����A���ۂ̓���Ƃ��ẮA�傫�ȕω��͂��蓾�܂���B
����ɁA�ꎟ���̓d���ω���B�_�̓d�����ς�邾���ŁAQ1 �̓d���ω��Ƃ͂Ȃ�܂���AQ1 �̑����͂قڈ��ŁA�͂��̓d���𗬂��Ă����Ύ�����܂��B
�g���b�L���O��H�ɂ����̂́A�A���v�̓d�������i�̉�H�Ƃ̌��ˍ����ŁA���x�p�����[�^�ł����ēd���ω����ω������Ƃ��ɁA2A3�o�͒i�ւ̃o�C�A�X�d�����ω����Ȃ��������䂷�邽�߂̔z���ł��B
�����d���������傫���Ȃ�ƁATr���������p�̒�d����H�̓d���������āA����ɔ����ďI�i�O���b�h�d�����㏸���ăo�C�A�X�d����������̂ŁA���̕������̓d�����傫������A�o�C�A�X�͕ς��Ȃ��A�Ƃ����킯�ł��B
�����̓d���c��Vs��R_m1�AR_m2 �Ō��܂�܂��B�����b�͕��̓d���c����ɂ��āAR_n1�AR_n2�Ō��܂�܂��B
�ŏ��́A����Tr��MOS-FET 2SJ117 ���g���Ă����̂ł����A�d�����肵�Ă�������܂����B
�����́A���������A�����̂�������MOS�̃Q�[�g�ɂ́A�I�V���̃v���[�u�ł��������Ă̓}�Y�C�炵���ł��B
���̉�H�ł́A�z�b�g���(�ʓd��)�́A�O���b�h�̓d�ʂ������̂ł��̏�Ԃő����̃v���[�u���Ȃ��ƁA���̗e�ʕ��ŏu�ԓI�ɋ}���ȓd�ʕϓ�������A�j��Ɏ���E�E�Ƃ��������̂悤�ł��B(\700�������̂ŁA���Ⴍ�ɏ���Ă���^^;;)
�C���������̂Ńo�C�|�[���ɂ��܂����B�o�C�|�[���͂����������͐����܂���B�x�[�X���̃C���s�[�_���X���Ⴂ����ł��B
���A�o�C�|�[����MOS�ł͉�������ω����܂��B�o�C�|�[���̕���(���̃Z�b�g�ł�)�_�炩�������܂����B
FET���ƁAe2�̊J��H�����������Ȃ�܂����A�J��H�̃C���s�[�_���X���傫��(������d���ł�yfs��������)�A�Œ�|�[�����ꌅ������̂ŁA���Ǔ����ł��B
Q2���o�͂̃R���f���T�Ƃō��|�[���́A1kHz�t�߂ł��B���̎��萔�ƌ덷������ō�鎞�萔�̊W����A�A�җʂ����肵�Ă��܂��BQ2���_�[�����g���ɂ��Ȃ������̂́A�A�җʂ����������Ċ댯�Ɣ��f��������ł��B
���݂ɁA100��F�̃R���f���T�����C���s�[�_���X�̐�Βl�́A100Hz�̗��_�l�łق�16���ł��B
���̒�d����H�̏o�̓C���s�[�_���X�́A�m����1���������܂�����A�N���X�g�[�N��Ƃ��ĊeCh���ɓd���R���f���T������̂́A�w�ǖ��Ӗ��ł��B
����Ȃ��Ƃ����Ă��A�C���s�[�_���X�̒ጸ���ʂ������͓̂���̎��g���ш�Ɍ����܂��B�܂�C���s�[�_���X�̂��˂���A���ꂪ�����I�Ȍ��Ƃ������A�����̕Ȃ݂����ȃ��m�ޏꍇ�����蓾��ł��傤�B
���ǂ̏��A��d���d��������ꍇ�A���͔z���̃C���_�N�^���X�ɂ��C���s�[�_���X�̏㏸�ł���A��e�ʃR���f���T�ɂ����ʂ͊��҂ł��܂���B���̂Ȃ�A�R���f���T�Ƃ������̂́A�����č���Ă���ȏ�͕K�����ȋ��U���g�������݂��܂����A�e�ʒl���傫���Ȃ�قNJ������͓��R������̂ł�����A��e�ʂقǎ��ȋ��U�_���������āA�����g�C���s�[�_���X�͂ނ��덂���Ȃ�킯�ł��B
�d���̍����g�C���s�[�_���X�̏㏸�́A�A���v�̋Ǖ��A�҂��܂ދA�ғ���̕s����v���ɂȂ�܂��B���ׂ̈ɁA�����I�ȉe��������̂ł����āA�����ĉ�X�l�ނ�1MHz�̉����Ă邩��ł͂���܂���B(����ᓖ����O������^^;;)
�����ɑ�e�ʃR���f���T������A��d���d����NFB�ɑ��Ă����Ȃ��炸�e����^���܂��B���ǁA���ꂪ��d���d���Ƃ��Ă̍Œ�|�[����^���邩��ł��B�������̃C���s�[�_���X�������g�ł͏オ���Ă��܂��킯�ł��B
�]���āA�g�[�^���Ƃ��Ă݂�Ȃ�A��d���̗����I�i�͕ʂƂ��āA�����i���ɑ�e�ʂ̓d���R���f���T��}������v�́A���A�Ҍ^�̒�d���d�����g��Ȃ��A�A�҂̃A���v�ł����d�v�ȈӖ������ƍl���Ă��܂��B
�����ł����A�֘A������Ƃ��āA�d����H�̍\���̎d���Ɠd�������i�̒萔�̑I���ɂ́A�����̑��֊W���K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����g�������l������Ȃ�A���R��R�l�Ȃǂ͑S�̂ɒႭ���������L���Ȃ킯�ł����A���̏ꍇ�ɂ͓d����H�̃C���s�[�_���X�Ɖߓn���������\���l�����Ȃ��ẮA�N���X�g�[�N��G���̖�肪�������Ĉ�������\��������܂��B
�ێ�I�ȓd����H���̗p����Ȃ�A�A���v��H���ێ�I�Ȓ萔�ݒ肪�K�v�ɂȂ�A�S�̂̃o�����X�����Ă���̂ł͖����ł��傤���H
�g�[�^���Ƃ��Ăǂ��炪�ǂ����́A������l���A�e�X�����Ŕ��f���ׂ����ł��傤�B����̑�햡���Ă�ł��B
���܂��̘b�B�ŏI�I�ȓd����H���A�}3�Ɏ����܂��B����́A�����Ȃ�ɔ[���ł����v�ł��B
GHz�I�[�_�[���l�������_����H�ł̍����g�G����(FCC�AFTZ��)�ł́A�p�X�R���Ɋ����Ē���ɒ��R��}�����邱�Ƃ�����܂��B
C�̎��ȋ��U�ɂ��Q���_���v���邱�ƂŁA�t�ɍL���ш�ŃC���s�[�_���X��������̂����R�̈�B������̗��R�̓R���f���T�͓d�͂�����Ȃ�����ł��B
�܂�AC�ɂ���ē��ꂽ�����Ō���ΎG���d�����������Ȃ����悤�Ɍ����Ă��A���̎G���d���͏����Ă��Ȃ��킯�ł�����A�ʂ̏ꏊ�ŎG���������������邱�Ƃ�����܂��B���������ꍇ�ɂ́A��R�ł��̎G���d�͂������̂��x�^�[�Ȃ̂ł��B�^��ǃA���v�ł́A�����̃X�i�o��H������ɑ������܂��B
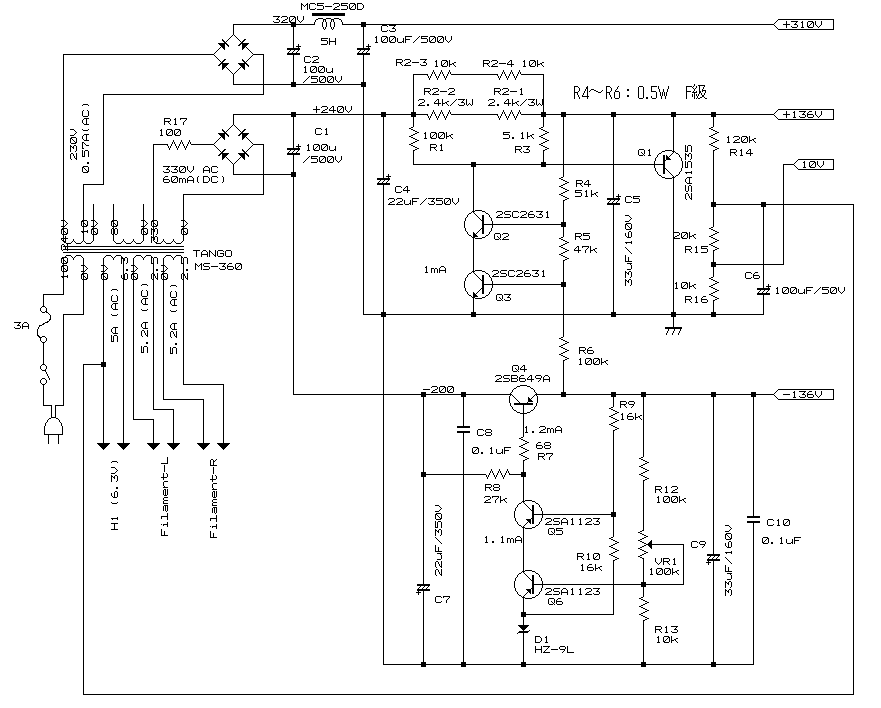
�T�@���x�v
�����ł�����A���RDC�h���t�g���o�܂��B
���߂́A�\���o�����X���Ƃ�����ŁA����R���g���Čy�������A���v�̃R���N�^����A�҂���Α��v���낤�E�E���炢�Ɏv���Ă���ł����A�Â������B2A3�O���b�h�Ō��Đ�V�h���t�g���܂����B���������肷��̂ɂ��Ȃ�̎��Ԃ��|����܂��B
�d���Ȃ��A�}篓���邱�ƂɂȂ����̂�DC�o�C�A�X�T�[�{��H�ł��B�\������ɂȂ�܂����B
�d���d���͉��x�I�Ɉ���łȂ��ƍ���܂��B�d���d�����ς��ƁA�I�i�o�C�A�X�d�����ς��܂��B
HZ-9L�ƃ}�C�i�X���̌덷����Tr��Vbe�̉��x�����́AHZ-9L�̕����͂��ɑ傫���̂ŁA�����ł͐��̕����Ƀh���t�g���܂��B�������A�A�Ғ�R�͕��̉��x�W���ł�����A�͂��ɕ��̕����Ƀh���t�g���܂��B���킹�Z��{�ŁA�d���o�̓h���t�g�͖w�ǖ����B
�A���A��d���d���̋A�Ғ�R�͋����疌��F���A-25ppm/���ȉ��ł��B
�����g���b�L���O�͊�d�ʂ��}�C�i�X�d���S�̂ł�����AVbe�͖��ɂȂ�܂���B�A�Ғ�R�l���㉺�łقړ����Ȃ̂ŁA�������h���t�g�v���ɂ͂Ȃ�܂���B�A�����x�͗v��܂�����A��͂�F���̋�����g���܂��B
���i��6DJ8�̒�d����CRD(��d���_�C�I�[�h)���g���Ă��܂��B4.5mA �� CRD �͓d���l�ɂ��Ȃ�̂��������A���x�ɑ��Ă����قǗǍD�ł͂���܂���B���A�ψ�������܂���A27k��/1W�̒�R���V���[�Y�ɓ���Ă��܂��B
�����͖{���Ȃ�|�W�X�^�ɂ��ׂ�(�疌��R�͉��x�W�������ł�����A���x�̕⏞�ɂ͂Ȃ�܂���)�ł����A���ۖ��Ƃ���C���ł�����A�����d���l���ς���Ă�����͂��܂�ς��Ȃ��̂ŁA��肠��܂���B
�����|�W�X�^������̂Ȃ�A3k��+1000ppm�̃��j�A���|�W�X�^�ƁA�J�[�{����24k��/1W�ŗǂ��Ǝv���܂��B���̏ꍇ��CRD
�̑I�ʂ����ēd���l�����߂�������ł��傤�B
�����ŏ����d��4.5mA�A����l��3.8mA�ł����B
��d���d����2SB649A�̑����́A1.3W���炢�ł�����AASO���猩�ĕ��M�킪�K�v�ł��B���͉��x80�����l�����Ă��A�s�̂̍ł����^�̂��̂ŗ]�T�\���ł��B���M��p�̐≏�V�[�g�����݁A�v���X�`�b�N���b�V�������܂��Ď��t���܂����B���M�펩�̂�GND�d�ʂɂ��Ă��܂��B�G�����Ƃ��Ɋ��d�������Ȃ��̂ŁB
�V�����g�� Tr �̕��M��͕s�K�v�ł��B�����̃V���[�Y��R�́A�͂t���ʂɓ�����\���ĕ��M���Ă��܂��B�V���[�Y��R�̔M���V�����gTr�ɓ`���Ȃ��ׂł��B
��R�̕��́A�M�I�ɐ����Ɨ]�T������܂����A3W�̒�R��1.5W�̓d�͂�H�킹��̂�0.5W�̒�R��0.25W�H�킹��̂ł́A�f�B���[�e�B���O�͓���50%�ł���������M�ʂ͑�Ⴂ�ŁA�O�҂̕��������ɂȂ�܂��B3W�̒�R�̕��������ɑς��邾���ł��B
���ǁA�傫�ȔM�ʂ̔����ɂ͏\���ȕ��M���l������Ƃ������Ƃł��B
�S�Ẵg�����W�X�^�͕K���������v�Z���āA���̑����Ŏ��͉��x80�����炢�܂Ŏg����̂��ǂ�����ASO���猟�����Ă��܂��B
����́A�����̂ł͕K�����ׂ����ł�����A������O�̎�����O�ɂ���������ŁA�G���\�[�Șb�ł͂���܂���B
����:����́A�����o���̏o�͂̕��ׂ����S�ɓƗ��ł���O�ɊǏo�͂ł̖��A�ғ����������Ȃ�A�ƌ����Ă��邾���ł��B���ۂ̏o�͂̕��ׂ͓Ɨ��ł͂���܂���B�ꎟ������k��1�Ō������Ă���̂ŁA�O�Ɋǃv���[�g�̔��]��������v���[�g�A�҂��|����܂��Bk��������A�҂��傫���Ȃ�A�̂Ɍ�������ŏI�I��rp�����͂l�������قnj��̓����ɋ߂��Ȃ�܂��B