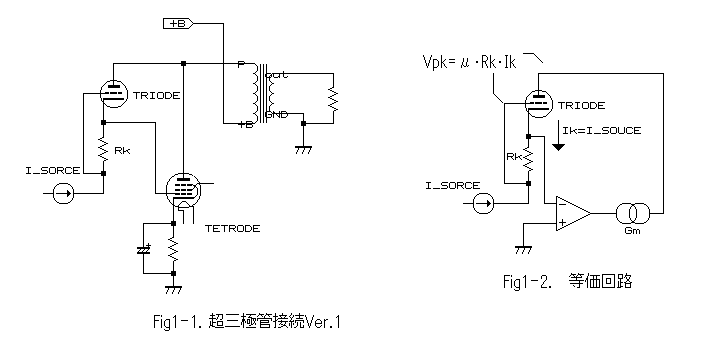
挻嶰嬌娗愙懕偺峫偊曽偲愝寁巜恓
乣僩儔儞僕僗僞悽戙偺偨傔偵乣
忋瀶巵偵傛偭偰奐敪偝傟偨乽挻嶰嬌娗愙懕乿偲偼丄嶰嬌娗傪揹埑婣娨慺巕偲偟偰梡偄傞偙偲偵傛傝丄揹椡憹暆抜偑屲嬌娗乮擳帄偼僩儔儞僕僗僞側偳偺揹棳惈弌椡慺巕乯偱傕丄偦偺婣娨偵梡偄偨嶰嬌娗偺摿惈傪嵞尰偝偣傞偙偲偱嶰嬌娗偺壒幙傪摼傞偲嫟偵丄怺偄PG婣娨偵傛偭偰嶰嬌娗偺傛偆側掅偄僾儗乕僩撪晹掞峈傪摼傞偙偲傪栚揑偲偟偨夞楬偱偡丅
(忋瀶巵偺僒僀僩偼儕儞僋儁乕僕傪偛嶲徠壓偝偄丅)
忋忦巵偺奐敪偟偨夞楬偵偼Ver1偐傜Ver5(VX偲尵偆偺傕偁傞)傑偱偁傝傑偡偑丄婎杮偲側傞Ver1偵偮偄偰愢柧偟傑偡丅
Ver1 偺婎杮揑側峫偊偐偨偑棟夝偱偒傟偽丄懠偼棟夝偱偒傑偡丅
巹偺挻嶰寢MX偩偭偰丄尒偨栚偺暋嶨偝傎偳柺搢側夞楬偱偼柍偄偺偱偡丅
偟偐偟側偑傜丄僩儔儞僕僗僞偟偐抦傜側偄悽戙偵偲偭偰偼丄偙偺棟夝偼梕堈側偙偲偱偼柍偄偱偟傚偆丅
棟夝傪崲擄偵偟偰偄傞嵟戝偺栤戣揰偼丄敿摫懱偺悽戙偵偲偭偰偼偦傕偦傕揹埑惈慺巕偱偁傞嶰嬌娗偑夝傝偯傜偄忋偵丄挻嶰寢偱偼偦偺巊偄曽偑旕忢偵摿庩偲偄偆偐丄摿挜揑偱偁傞偙偲偱偟傚偆丅
偦偙偱僩儔儞僕僗僞悽戙偺偨傔偺挻嶰寢夝愢傪傗傝偨偄偲巚偄傑偡丅
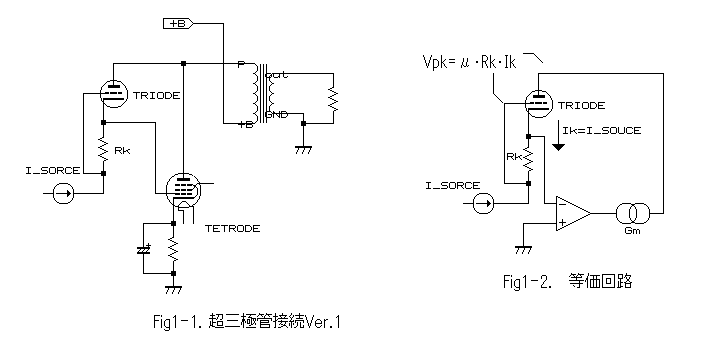
偙傟偑婎杮揑側夞楬峔惉偱偡丅摍壙夞楬傕摨帪偵帵偟傑偡偑丄嫲傜偔偼丄僩儔儞僕僗僞偵姷傟偨悽戙偵偲偭偰偼丄偙偺嶰嬌娗偺揹埑婣娨偑乽壗偺帠傗傜偝偭傁傝乿偩偲巚偄傑偡丅
弌椡偺屲嬌娗(Tetrode)偺摦嶌偼丄僨傿僾儗僢僔儑儞儌乕僪偺FET偲摨條偵峫偊偰娫堘偄偁傝傑偣傫偺偱丄徻嵶偼妱垽偟傑偡丅
梫偡傞偵丄揹棳惈偺弌椡娗偩偲夝傟偽丄偦傟偱OK偱偡丅
愭偢偼丄朤擬宆偺乽嶰嬌娗乿偲偄偆傕偺偑偳偺傛偆側摦嶌傪偡傞傕偺側偺偐傪棟夝偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅
偙傟偼丄僩儔儞僕僗僞偲偄偆揹棳憹暆慺巕偵姷傟偨悽戙偵偲偭偰尒傞側傜丄乽揹埑偱儌僲傪峫偊傞乿偲偄偆栵夘傪攚晧偄崬傓偙偲偵側傝傑偡丅
悢幃偼偁傑傝巊傢偢偵丄戝晹暘偑掕惈揑側愢柧偱偡偐傜丄寵偑傜偢偵撉傫偱壓偝偄偹丅
僇僜乕僪偺拞偵偼僸乕僞乕偑擖偭偰偄偰丄偙傟偑柧傞偔婸偄偰偄傑偡丅偙偺僸乕僞乕偵傛偭偰丄僇僜乕僪偑擬偣傜傟傑偡丅柤慜偺捠傝丄僸乕僞乕偼僇僜乕僪傪僸乕僩偡傞摴嬶偱偡丅
僸乕僞乕偵傛偭偰擬偣傜傟偨僇僜乕僪偐傜偼丄乽擬揹巕乿偲屇偽傟傞揹巕偑旘傃弌偟偰偒傑偡丅
暔棟妛揑偵尵偊偽丄偙傟偼擬偲岝偺僄僱儖僊乕偵傛偭偰帺桼揹巕偑塣摦僄僱儖僊乕傪摼傞丄偲娙扨偵峫偊偰壓偝偄丅
(尩枾偵暔棟嶌梡傪棟夝偡傞偵偼丄Maxwell 曽掱幃偲検巕椡妛偺曌嫮偑昁梫偱偡丅傗傝偨偄恖偼偳偆偧丅)
偩偐傜丄僇僜乕僪偐傜旘傃弌偡揹巕偺検傪憹傗偡堊偵偼丄尵偄姺偊傞偲揹棳傪懡偔棳偡偨傔偵偼丄僸乕僞乕偵戝揹椡傪怘傢偣傞昁梫偑弌偰棃傞栿偱偡丅
偱丄揹巕偼儅僀僫僗偺揹壸傪帩偮偺偱偡偐傜丄偦偺擬揹巕傪堷偒晅偗傞偨傔偵偼丄僾儔僗偺揹埵偑偁傟偽偦偙偵岦偐偭偰擬揹巕偑旘傃偮偄偰棃傞栿偱丄偙傟偑僾儗乕僩偺栶栚偱偡丅
偮傑傝丄娙扨偵尵偊偽僾儗乕僩偐傜僇僜乕僪偵揹棳偑棳傟傞偺偱偡丅
偙偺揹棳傪僐儞僩儘乕儖偡傞偺偑僌儕僢僪偱偡丅僌儕僢僪偵偼僇僜乕僪偐傜尒偰晧偺揹埵傪梌偊傑偡丅
崅偄惓偺揹埵傪帩偮僾儗乕僩偵旘傃偮偙偆偲偡傞擬揹巕傪丄晧偺揹埵偱幾杺偡傞帠偱僐儞僩儘乕儖偡傞偺偱偡丅
偩偐傜丄婎杮揑偵偼僌儕僢僪乣僇僜乕僪娫偺揹埑傪曄偊傞帠偱丄僾儗乕僩乣僇僜乕僪偵棳傟傞揹棳偑惂屼偱偒傞栿偱偡偑丄摉慠側偑傜僾儗乕僩偺揹埵偑崅偗傟偽丄偦偙偵岦偐偭偰揹巕傪堷偒晅偗傞椡偼嫮偔側傝傑偡丅
寢榑偲偟偰丄僾儗乕僩乣僇僜乕僪娫揹埑(Vpk)丄僌儕僢僪乣僇僜乕僪娫揹埑(Vgk)偺偳偪傜傕揹棳傪曄壔偝偣傑偡丅
偱偡偐傜丄僾儗乕僩乣僇僜乕僪偺揹棳(Ip)偲揹埑偺娫偵偼斾椺掕悢偑偁傞偺偱偡丅偙傟偑rp偱偡丅
Vgk偲僾儗乕僩乣僇僜乕僪偺揹棳偲揹埑偺娫偵傕斾椺娭學偑偁傝傑偡偹丅偙傟偑gm偱偡丅
偙偙偺強傪愭偢廫暘偵棟夝偟偰壓偝偄丅
崱丄僾儗乕僩懁偵揹埑傪梌偊偰偄傞栿偱偡偑丄偙偺僾儗乕僩懁偺揹埑尮偵崅偄掞峈抣偑偁傞丄偲偟傑偟傚偆丅
偙偺帪僾儗乕僩偵敪惗偡傞揹埑偲Vgk偲偺娫偵傕斾椺掕悢偑偁傝傑偡丅偙傟偑兪偱偡丅
尵偄姺偊傞偲丄撪晹掞峈rp偵揹棳Ip偑棳傟傞帠偱丄偦偺揹棳Ip偵斾椺偟偨揹埑偑rp偵懳偟偰敪惗偡傞栿偱偡丅
暿偺尵偄曽傪偡傞側傜丄rp偑廫暘偵彫偝偗傟偽丄Vgk偱Vpk傪惂屼偡傞揹埑弌椡惂屼慺巕偱偁傞丄偲尵偆偙偲偱偡丅
偦偺斾椺掕悢丄偮傑傝弌椡揹埑偲擖椡揹埑偺斾椺掕悢偑兪偱偁傞丄偲偄偆尒曽傕弌棃傑偡丅
廬偭偰丄嶰嬌娗偺僇僜乕僪愙抧夞楬偵偍偄偰丄傕偟傕掕揹棳尮傪僾儗乕僩偵愙懕偡傟偽丄弌椡僀儞僺乕僟儞僗偼rp偱憹暆棪偼兪偱偡丅
偙傟偑敿摫懱偲嶰嬌娗偺嵟傕戝偒側摿惈偺堘偄偱偡丅
幃偵彂偄偰傑偲傔傞偲
rp偵Ip偑棳傟傞偙偲偱丄揹埑Vpk偑敪惗偡傞偺偱偡偐傜丄Ipp=Vpk
兪偼Vgk偲Vpk偺斾椺掕悢偱偡偐傜丄Vpk=兪gk
gm偼Ip偲Vgk偺斾椺掕悢偱偡偐傜丄Vgkm=Ip
偩偐傜丄憹暆棪兪=rpm 偱偡丅
偙偙偱丄嶰嬌娗偺惷摿惈丄Ip-Vpk摿惈乮僾儗乕僩摿惈乯傪尒偰傒傑偟傚偆丅
(偙偺僌儔僼偼儌僨儖壔偟偨傕偺偱丄偙傫側偵棟憐揑側嶰嬌娗偼丄幚嵺偵偼懚嵼偟傑偣傫偺偱拲堄偟偰壓偝偄丅)
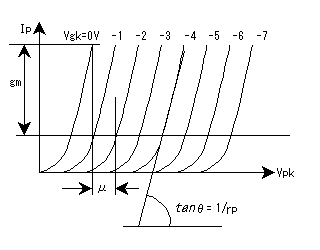
恾偺幬傔偺慄偑戲嶳偁傞偺偼丄Vgk偵傛傞堘偄傪昞偟偰偄傑偡丅墶幉偑Vpk丄廲幉偑僾儗乕僩揹棳Ip偱偡丅
恾偐傜傕棟夝偱偒傞偲巚偄傑偡偑丄婎杮揑偵偼Vgk偱Vpk偑惂屼偝傟偰偄傞偺偱偡偑丄偳傟堦偮偑曄壔偟偰傕懠偺僷儔儊乕僞偵塭嬁傪梌偊傑偡丅偦偺娭學傪堦媊揑偵昞偟偨偺偑偙偺恾偱偡丅
Vpk偲Ip偺娭學傪帵偡斾椺掕悢偑rp偱偡偐傜丄偙傟偼偙偺幬傔慄偺孹偒傪帵偟偰偄傞偲尵偊傑偡丅
愭傎偳偺嶰掕悢偺幃偱尵偆側傜偽丄兪=rpm偱偡偐傜丄rp=兪/gm偱偡傛偹丅
偮傑傝丄偙偺恾偼婛偵愢柧偟偨嶰偮偺斾椺掕悢傪恾幃揑偵昞尰偟偨偩偗偱偡丅
偙傟偵懳偟偰丄晧壸捈慄(Load line)偲偄偆傕偺傪梌偊傑偡丅偙傟偼丄堦斒揑偵偼晧壸掞峈偺堄枴偱棟夝偝傟偰偄傞帠偲巚偄傑偡偑丄昁偢偟傕丄偄偮傕偦偆偱偁傞偲偼尵偊傑偣傫丅
挻嶰寢偱偼丄僇僜乕僪懁偑揹棳惈(僀儞僺乕僟儞僗偑亣)偱偡偐傜丄揹棳抣偼僇僜乕僪懁偱堦媊揑偵寛掕偝傟傑偡丅偩偐傜晧壸掞峈抣偱曄壔偡傞栿偱偼柍偄偺偱偡丅
揹棳尮偱偁傞偲塢偆偙偲偲丄怣崋尮僀儞僺乕僟儞僗偑柍尷戝偱偁傞偙偲偼摍壙偱偡丅掕揹棳偲偼丄揹埑偵埶傜偢堦掕偺揹棳傪棳偡帠偱偡丅
偳傫側偵崅揹埑偱傕偳傫側偵掅揹埑偱傕丄堦掕偺揹棳傪棳偡帠偱偡偐傜丄尵偄懼偊傟偽掞峈偲暘埑夞楬傪嶌偭偨偲偒偵晧壸掞峈偑崅偐傟掅偐傟丄晧壸掞峈偺抣偩偗偱掞峈椉抂偺揹埑抣偑寛傑傞帠偵側傝傑偡丅偙傟偼撪晹僀儞僺乕僟儞僗偑嬌抂偵崅偄偙偲偵懠側傝傑偣傫丅傕偟撪晹僀儞僺乕僟儞僗偑掅偗傟偽丄偦偺撪晹掞峈偲偺娫偱暘埑偑惗偠傞偐傜丄偐偐偭偰偄傞揹埑偵傛偭偰堘偄偑惗偠丄掞峈偺抣偩偗偱偼暘埑抣偑寛傑傜側偄偙偲偵側傝傑偡偐傜丅
廬偭偰丄揹埑抣偵埶傜偢偵堦掕偺揹棳偑棳傟傞夞楬偼丄撪晹僀儞僺乕僟儞僗偑柍尷戝偲尒側偣傞偺偱偡丅揹棳惈偺怣崋尮偲偄偆偺偼丄偙偺掕揹棳尮偑怣崋偱惂屼偝傟偰偄傞乮亖怣崋偵廬偭偰揹棳偑曄壔偟偰偄傞乯忬懺偱偡丅僌儕僢僪偵怣崋傪擖傟偨僇僜乕僪愙抧偺屲嬌娗偺僾儗乕僩偑偙傟偵憡摉偟傑偡丅
偙偙偱丄挻嶰嬌娗愙懕偺婣娨娗偺儘乕僪儔僀儞偲偦偺摦嶌偵偮偄偰峫偊偰尒傞帠偲偟傑偟傚偆丅
婣娨娗偲偄偆偺偼丄嵟弶偺恾侾偱帵偟偨丄弌椡娗偺僾儗乕僩乣僌儕僢僪娫偵偮側偄偩嶰嬌娗偱丄偙傟偑弌椡娗偵晧婣娨傪妡偗偰偄傞偺偱丄偙偆屇傫偱偄傑偡丅壗偑偳偆晧婣娨側偺偐偼偍偄偍偄愢柧偟傑偡丅
愭偵帵偟偨嶰嬌娗偵墬偄偰丄崱壖偵Vpk=100V偺帪偵揹棳偑2mA棳傟偰丄偦偺帪偺Vgk偑-4V偩偭偨丄偲偟傑偟傚偆丅
娫堘偄側偔丄揹棳偑0mA偺帪偵偼偳傫側掞峈抣偱傕Vgk=0V偱偡丅偩偐傜尨揰傪捠傝傑偡丅
Vgk=Ipk 偱偡偐傜丄偙偺帪偺Rk偼2k兌偱偡丅
壖偵僾儗乕僩偺揹埵偑偦偺傑傑偱丄揹棳抣偑2.5mA偵憹偊傟偽丄揹棳抣偵斾椺偟偨Vgk偑敪惗偟傑偡丅
Vgk=2k亊2.5mA偱偡偐傜丄-5V偱偡丅偙傟偑惵娵偺揰偱偡丅
恾偐傜丄Ip偑2.5mA偱丄Vgk偑-5V偺帪偵偼Vpk偼120V偱側偄偲崲傞帠偵側傝傑偡偑丄婣娨娗偺僾儗乕僩揹埵偑寛傑偭偰偄傟偽丄偙傟偼婣娨娗偺僇僜乕僪偺揹埵偑曄傢傞偟偐偁傝傑偣傫丅婣娨娗偺僇僜乕僪揹埵(懳傾乕僗揹埵)偼掕揹棳尮偲屲嬌娗偺僌儕僢僪偑偮側偑偭偰偄傑偡偐傜丄揹埵偼晄掕偱偡丅偦偺揹埵偺曄壔偱婣娨娗偺Vpk偼120V偵側傠偆偲偡傞栿偱偡丅
寢壥偲偟偰丄廔抜屲嬌娗偺僌儕僢僪擖椡揹埵偑曄壔偟傑偡丅廔抜偺揹棳抣偼丄婎杮揑偵Vgk偩偗偱寛傑傝傑偡丅
寢嬊丄廔抜偺屲嬌娗偱尒偰Vp=120V偺揹埑偑敪惗偡傞傛偆偵丄廔抜偺屲嬌娗偺揹棳傪曄偊傛偆偲偲偡傞栿偱偡丅
偙偙偱傕偆堦搙恾侾傪尒偰壓偝偄丅
懄偪丄挻嶰嬌娗愙懕偱偼偦偺婣娨揹埑偵尒崌偭偨揹棳偑廔抜偵棳傟傛偆偲偡傞偺偱偡丅壗屘側傜丄廔抜偺屲嬌娗偼僌儕僢僪揹埵偑寛傑偭偰偍傜偢丄僼儘乕僥傿儞僌偵側偭偰偄傑偡偹丅擖椡偑揹埑偱偼側偔揹棳偵側偭偰偄傞偐傜偱偡丅
偩偐傜丄婣娨揹埑偑寛傑偭偨帪偵弶傔偰僌儕僢僪揹埵偑寛掕偡傞偺偱偡丅
偙傟傪丄乽100%偺揹埑婣娨乿偲尵偄傑偡丅
壗屘100%側偺偐偲偄偆偲丄摍壙夞楬偺曽傪尒偰栣偆偲夝傞偲巚偄傑偡偑丄擖椡懁偑僀儞僺乕僟儞僗柍尷戝偱丄婣娨懁偑偁傞堦掕偺僀儞僺乕僟儞僗亅嶰嬌娗偺rp亅偩偐傜偱偡丅尵偭偰傒傟偽丄棙摼偺戝偒側OP傾儞僾偩偭偰偙偆側傝傑偡丅
寢嬊丄偙偺愒娵偺揰偲惵娵偺揰傪寢傫偱弌棃傞捈慄偺忋偱摦嶌偡傞帠偵側傝傑偡丅偙傟偑婣娨娗偺儘乕僪儔僀儞偱偡丅
偙偙偱丄婣娨嶰嬌娗偺僾儗乕僩揹棳Ip亖擖椡揹棳I_SOURCE偱偁傞偙偲偵拲堄偟偰壓偝偄丅
婛偵偍婥偯偒偺帠偲巚偄傑偡偑丄偙偺儘乕僪儔僀儞偼擖椡揹棳偲丄弌椡揹埑偺娭學傪帵偟偰偄傑偡丅
偮傑傝丄擖椡揹棳偺曄壔偵懳偟偰丄傾儞僾慡懱偺弌椡揹埑偼偙偺儘乕僪儔僀儞偺忋傪堏摦偡傞帠偵側傞偺偱偡丅
晧壸偵傛傜偢偵偁傞乽弌椡揹埑乿傪敪惗偡傞偲尵偭偰傕丄傑偝偐晧婣娨偱挻揱摫偑弌棃傞栿偱偼偁傝傑偣傫偐傜丄摉慠丄偁傞撪晹掞峈傪帩偪傑偡丅
撪晹掞峈偼偦偺弌椡娗偺摿惈偱寛傑傝傑偡丅婛偵愢柧偟偨傛偆偵丄100%揹埑婣娨偱偁傞丄偲尵偆帠偼弌椡娗偺gm偱寛傑傞婣娨棪偵撪晹掞峈偑埶懚偡傞帠傪帵偟偰偄傑偡丅
晧壸掞峈抣傪RL偲偟偨偲偒丄弌椡偵敪惗偡傞揹埑偼gmL偱偡偐傜丄RL/(gmL)=1/gm偑撪晹掞峈偱偡丅
gm偑崅偄傎偳丄廔抜偺僆乕僾儞僎僀儞偼憹偊傑偡偹丅
憹暆棪偼兪偱堦掕偱偡偐傜丄gm偑崅偗傟偽偦偺暘NFB検偼憹偊傞帠偵側傝丄摉慠弌椡僀儞僺乕僟儞僗偼尭傞傢偗偱偡丅
偙傟傜偐傜丄恾1偵帵偟偨夞楬慡懱傪堦偮偺憹暆婍偲偟偰尒偨帪偺摿惈偑敾傝傑偡丅
愭偵愢柧偟偨傛偆偵丄撪晹掞峈偲偼Vpk偲Ip偺斾椺掕悢偱偡丅偩偐傜丄恾幃揑偵偼1/gm偺孹偒傪帩偮捈慄偱嬤帡偱偒傑偡丅
偦偺帪偺憹暆棪偼忋偵帵偟偨婣娨娗偺儘乕僪儔僀儞偵忔偭偰偄側偗傟偽側傝傑偣傫丅廬偭偰丄奣棯兪偱寛掕偡傞帠偵側傝傑偡丅
偙傟偵丄幚嵺偺晧壸掞峈RL偺儘乕僪儔僀儞傪堷偄偨偺偑壓恾偱偡丅
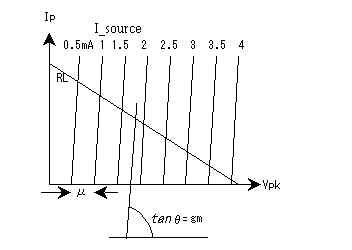
栜榑丄RL偺寛掕偼丄尦偺屲嬌娗偺惷摿惈偺尐偺摿惈偲丄棳偣傞揹棳抣丄嵟戝僾儗乕僩懝幐偐傜寛傔偨僶僀傾僗揹棳抣摍傪姩埬偟偰寛掕偟傑偡偐傜丄偙偺僾儘僙僗帺懱偼捠忢偺愙懕曽朄偲壗傜曄傢傞帠偼偁傝傑偣傫丅
偙偺寛掕偺巇曽偼丄揹棳惈弌椡慺巕側傜壗偱傕摨偠傛偆側傕偺偱偡丅
晧婣娨偼杺朄偱偼偁傝傑偣傫偐傜丄摉慠偲偄偊偽摉慠偱偡偑丄尦偺屲嬌娗偺摿惈偑曄壔偟偨栿偱偼側偄偺偱偡丅晧婣娨偵傛偭偰丄偙偆偄偆摿惈偵側傞傛偆偵丄僌儕僢僪揹埑偑惂屼偝傟偰偄傞偩偗偱偡丅
廔抜偺僾儗乕僩乣僌儕僢僪娫偺揹埑偑嶰嬌娗偺兪偱寛掕偡傞偐傜丄廔抜偺僌儕僢僪揹埑偼忋恾偵側傞傛偆偵彑庤偵偒傑傞偲尵偆偙偲偱偡丅
屻偼丄偙偺擖椡揹棳I_source傪摼傞庤懕偒偱偡偑丄敿摫懱偺夝傞恖側傜偙傟偼娙扨偱偟傚偆丅
椺偊偽僄儈僢僞愙抧偺僄儈僢僞掞峈傪嵟戝擖椡揹埑偲昁梫側弌椡揹棳偵尒崌偭偨抣偵偡傟偽丄僐儗僋僞偵偼擖椡揹埑偵斾椺偟偨揹棳偑棳傟傞帠偵側傝傑偡傛偹丅娙扨偵偼丄偙傟偱OK偱偡丅
愝寁偡傞偨傔偵偼丄傑偢揹尮僩儔儞僗偱寛傑傞揹尮揹埑偑偁傝傑偡偹丅
幚嵺栤戣偲偟偰丄搒崌偺椙偄僩儔儞僗傪攧偭偰傞偲偼尷傜側偄傢偗偱偟偰丄嬤偄僩儔儞僗偱娫偵偁傢偣傞偟偐柍偄偲巚偆傫偱偡丅
偩偐傜丄巊梡偡傞屲嬌娗側傝價乕儉娗側傝偺摿惈偵偁偭偨揹尮僩儔儞僗傪寛傔傑偡丅
偙偙偱丄揹尮偺DC揹埑丄偮傑傝僾儗乕僩揹埑偑傑偢寛傑傞偲巚偄傑偡丅
師偵弌椡偺屲嬌娗偺仸嵟戝懝幐偐傜丄僾儗乕僩摿惈偵儘乕僪儔僀儞傪堷偄偰丄摦嶌揰傪寛傔偰傗傟偽丄僇僜乕僪偺揹埵偑寛傑傝傑偡丅偡傞偲昁慠揑偵弌椡娗偺僇僜乕僪掞峈抣偑寛傑傝傑偡丅
傑偨丄偦偺僶僀傾僗揹棳抣偵墬偗傞僌儕僢僪揹埵傕寛傑傝傑偡偹丅
偦偙偱丄僾儗乕僩乣僌儕僢僪娫偺揹埵嵎偑寛傑傝傑偟偨丅偙傟傪尦偵婣娨娗偺摦嶌揰傪寛傔傑偡丅偙偺揹埑偵側傞傛偆側捈慄傪捠傝丄偐偮捈慄惈偺椙偝偦偆側丄偮傑傝兪偑側傞傋偔堦掕側傞傛偆側孹偒傪扵偡偺偱偡丅
偙偆偡傟偽丄婣娨娗偺摦嶌揹棳偲Rk偑寛傑傝傑偡丅
偙傟傪尦偵偟偰丄弶抜傪寛傔傑偡丅弶抜偺僶僀傾僗揹棳偼忋偺摦嶌揰偱寛傑傝傑偡偐傜丄屻偼擖椡揹埑乣揹棳曄姺棙摼偱偡丅
壖偵弶抜偵僩儔儞僕僗僞傪巊偆傕偺偲偟傑偡丅寛傑偭偰偄側偄偺偼僄儈僢僞掞峈Re偩偗偱偡偹丅
娙扨偵峫偊傟偽丄僩儔儞僗偺僀儞僺乕僟儞僗傪RT丄僗僺乕僇乕傪8兌偲偡傞偲偒丄併(RT/8)偑姫慄斾偱偡偐傜丄僩儔儞僗偱幐傢傟傞揹埑棙摼偼
1/併(8/RT)偱偡丅(僩儔儞僗偱揹椡偼幐傢傟傑偣傫偐傜丄揹棳偑憹偊傑偡丅)
偩偐傜丄(婣娨娗偺兪)亊(Rk/Re)/{併(8/RT)}丂偑嵟廔揑側揹埑棙摼偵側傝傑偡丅偩偐傜丄椺偊偽擖椡1Vrms偱嵟戝弌椡偲偡傞側傜丄偙偺揹埑棙摼偑嵟戝弌椡揹埑偵側傞條偵偡傟偽椙偄傢偗偱偡丅
(幚嵺偵偼僩儔儞僗偺懝幐傕偁傝傑偡偐傜丄偙偺幃偺0.9攞偲偐偵側傞偱偟傚偆丅)
寛傔庤偼丄(巹偺峫偊偲偟偰偼)廔抜偺僾儗乕僩揹埑偺曽偐傜寛傔偰偄偔丄師偵婣娨娗偺摦嶌傪寛掕偡傞丄偲尵偆偙偲丅
弶抜偐傜寛傔傞偙偲偼弌棃側偄偺偱偼側偄偐丄偲巚偭偰偄傑偡丅
巹偺愝寁偟偨椺(6BM8僔儞僌儖)偱偼丄偙偺愝寁朄偲偼彮偟堘偭偰偄傑偡丅婣娨娗偺儘乕僪儔僀儞偑尨揰傪捠偭偰偄傑偣傫丅
偙傟偼丄2A3-PP偱傕摨偠偱偡丅堦悺偢傜偟偰慄宍惈傪媮傔傞丄偲偄偆僥僋僯僢僋偱偡丅
偝傎偳擄偟偄夞楬偱偼偁傝傑偣傫偐傜丄偠偭偔傝峫偊傟偽棟夝偱偒傞傕偺偲巚偄傑偡丅
扤偐偵夝傞偺偱偁傟偽丄扤偱傕夝傞両愭偢偼偦偆怣偠偰傒偰壓偝偄(^^;/丅
帺暘偱峫偊傞慜偵乽夝傜側偄傕偺偱偁傞乿偲怣偠偰偟傑偆恖偺丄側傫偲懡偄偙偲偐両
乽偙偙偑夝傜傫偧両乿偲尵偆曽丄儊乕儖傪壓偝偄丅
仸幚嵺偺懡嬌弌椡娗偺懡偔偼丄僾儗乕僩懝幐傛傝傕SG懝幐偑栤戣偵側傞帠偑懡偄偺偱丄椙偔婯奿傪撉傫偱偐傜愝寁偟偰壓偝偄丅