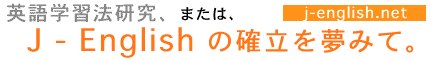
| <詳しくチェック>asの特殊な使い方 | |
講義トップへ戻る 元の英文へ戻る 次の英文へ 講義の学習の仕方 英文法則の全体像 講義の内容について質問 |
The deceased were identified as 26-year-old female swimming instructor Mai Kuramoto and 36-year-old fishing gear maker Yuji Fujimoto. 上の英文の構造は、
イメージ1+「副-前置詞句」と考えることができます。asは前置詞として使いますので「副-前置詞句」の部分は「前置詞+名詞」という形になっていますね。 ただ、asという単語は、英語の単語の中で最も用法が多い単語なので、一筋縄ではいきません。たとえば、次の英文を見てください。 We regard the rumor as doubtful. *regard<動詞3>みなす 「私たちは、その噂を疑わしいと考えている。」という意味の英文です。この英文の構造を考えてみましょう。 イメージ3+「副-前置詞句」のようにも思えます。上の英文と同じ考え方です。しかし、ちょっとおかしいですね。どこがおかしいのかというと、「副-前置詞句」の構造が「前置詞+形容詞」となっているところです。 前置詞は、「名詞の前に置く言葉」なので、「前置詞+名詞」という形なるはずで、「前置詞+形容詞」という形には基本的にはなりません。ということは、このasは前置詞とは少し考え方を変えなければならないということです。 では、このasは何なのかというと、「B’を導くas」ということになります。どういうことか説明しましょう。 たとえば、もしregardという動詞をイメージ5の英文で使えるなら、
と表現することができますね。これで「私たちは、その噂は疑わしいと考えている。」という意味を表現することができます。 しかし、残念ながらregardという動詞はイメージ5の英文では使うことができず、イメージ3の英文を使うしかありません。その場合に、イメージ5のようにいきなりdoubtfulという形容詞をおくことはできないので、その前に「B’を導くas」をおいて、実質的にイメージ5と同じイメージの型であることを示すわけですね。 したがって、この英文は、イメージの型としては、先ほどのようなイメージ3+「副-前置詞句」と捉えるよりも、
イメージ5の特殊形と捉えた方が、「イメージの型」理論としてはぴったりとするわけです。 そう考えれば、先ほどの英文でも、
イメージ2(イメージ5の受け身)として考えると、A’がAの状態を説明していることがよくわかりますね。こちらは受け身なので、asがA’を導く形になりますが。 元の受け身ではない英文でも、
イメージ5で捉えれば、B’がBの状態を説明していることが「イメージの型」によって自然に理解できると思います。 では、同様に「B’を導くas」が使われている英文を見てみましょう。その英文の表しているイメージを「イメージの型」で捉えることに注意してくださいね。 <例文1>
「副-サイン節」+イメージ5という形ですね。ただ、takeという動詞が、そのままではイメージ5の形をとれないので、asがB’の前に置かれています。BとB’の間には、 it is a warning to Japan という関係があるので、イメージ5の型で理解できますね。
「そのロケットは起爆装置を持っていなかったので、政府関係者は、それを日本への警告として受け取った。」 <例文2>
イメージ3+イメージ5ですね。ただ、イメージ5の方は、depictという動詞がイメージ3でしか使えないので、B’の前にasがついています。特に、この英文の場合は、asの後ろが「形容-分詞句」になっているので、asを前置詞と考えることは難しいですね。やはり、この形は、 Japanese wartime actions are aimed at liberating other parts of Asia という意味として捉えた方がわかりやすいでしょう。これなら「日本の戦時中の行動は、アジアの他の地域を解放することに向けられている」という意味関係がよくわかります。
「それらの教科書は、日本軍のための女性の性的奴隷化を無視して、日本の戦時中の行動をアジアの他の地域を解放することに向けられたものとして描いている。」 <例文3>
全体としてはイメージ2+「副-前置詞句」です。その「副-前置詞句」の中の名詞は「名-ing句」になっていて、その内部構造は、
イメージ2+「副-サイン節」となっています。やはり、A’の前にはasがついています。この部分の「中国に対して意気地なしの」という形容詞は、Aの「政府」の状態を説明している部分ですね。
「政府は、もし抗議を申し出なければ、中国に対して意気地なしと見られることを明らかに恐れていた。」 |