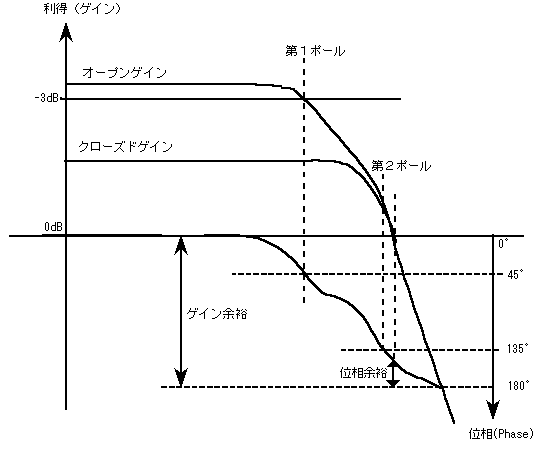
図1. ボーデ線図
NFB−Negative Feed Back−日本語で言えば負帰還。
その効能とか弊害については、既に多くの本やHPでさんざん目にされていることと思います。
しかし、その安定度と実質的な動作については、あまり目にしないようなので、ここで負帰還の安定度について、簡単に触れてみたいと思います。
負帰還増幅器の安定度は様々なファクターで決まります。そのうち幾つかについて述べてみたいと思います。
1.スタガ比と安定性
先ず問題になるのが、スタガ比です。スタガ比とは、各増幅段の持つ時定数で決まる、極(ポール)の周波数比のことです。
DCアンプでは高域だけで決まりますが、真空管アンプ−特に出力トランス付き−の場合は低域の方がより大きな問題になり易いでしょう。尚、時定数とポール(極)についてはここに書いております。
この差が大きいほど、一般には安定になります。これは、ボーデ腺図(Bode
chart)から解ります。
高域時定数を例に取った場合を下図1に示します。ここに示すように、ボーデ腺図から位相回転を知る事が出来ます。
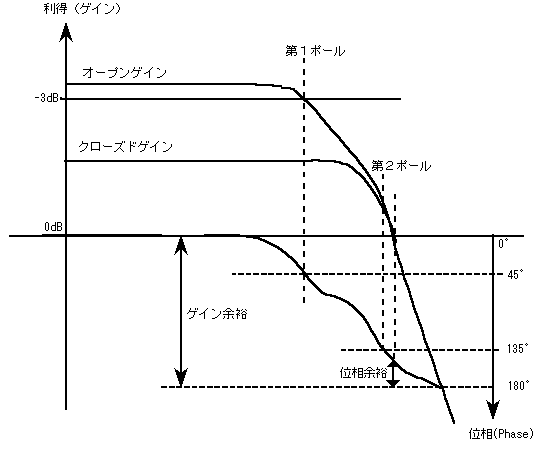
図1. ボーデ線図
負帰還の入力は出力×βですから、簡単に言って、その出力の位相が180度回れば正帰還になるわけです。基本的には、これがNFBアンプが発振する理由です。
しかし、もしも180°位相が回転した時の出力ゲインが0dB以下であれば、出力が戻ってきてさらに大きくなるという悪循環に陥る事はないので、発振には至りません。この条件を考えれば良いのです。
(尚これは、ラプラス平面の左半平面上に全ての極がある、と言うのと等価です。)
この裸利得が0dB迄下がった時の位相角と180°の差を位相余裕(Phase Margin)と言います。要するに、発振に至るまでには、これだけの位相角の余裕がありますよ、と言うことです。
また、180°に達した時のマイナスゲインの幅をゲイン余裕(Gain Margin)と言います。ゲイン又はNFB量がマージン分だけ増えれば発振するわけです。
しかし、これらがぎりぎりでも発振には至らないのか?と言うとそうではありません。実際問題として、位相余裕が5°のアンプなんて、マトモに動くわけありません。30°くらいは欲しいところです。
十分に安定であるかどうかは、これで解ります。しかし、それは必ずしもそれは最適な過渡応答性を示してはいません。発振はしない、と言うだけです。
最適な過渡応答は、次式により計算する事が出来ます。簡単のため、高域時定数が二つの場合を考えます。
と言っても、一般の方には少々面倒な計算かもしれませんが、まぁ気楽に読んで下さいな。
二つの時定数をそれぞれ T0,T1 、また総合利得をA、負帰還をβとする。実際に計算してみると解りますが、深いNFBを掛けようとすれば、とんでもなく大きなスタガ比が必要である事が解ります。
この時、伝達関数は次式で与えられる。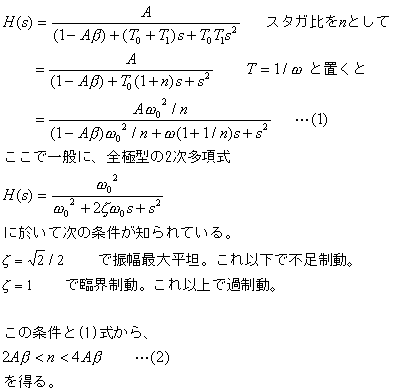
(老婆心までに付け加えると、3つ以上の有意な時定数を持つアンプで、深いNFBを掛けるのはアマチュアには無理があります。同じ理由で、2ポール位相補償なんかに安易に手を出すと、ヤケドしますよ。)
勿論、第二ポールをより高い周波数に追いやる事も重要です。
しかしながら、高い周波数に追いやるといっても、10MHzを実現するのは簡単ではありません。
紙の上での計算上では30MHzにだって出来るでしょうけど、神業と言えるくらいの実装技術でもお持ちでない限り、そんな数字は絵に書いた餅に過ぎません。現実には、浮遊容量による問題や、抵抗やコンデンサが持つ素子自身の特性等から大幅な制約を受ける事になります。
(各増幅段のインピーダンス整合を取れば出来ます。高周波回路ではそうやっています。)
従って、もし仮に広い帯域で一定の負帰還をかけて、尚且つその過渡応答を最適にしようとするなら、帰還量を減らさざるを得ないのです。
特にアマチュアの場合には、一般的に言って実装技術でも劣っている場合が多いわけですから、尚更です。
また、関連する事柄として、増幅段の数や形式があります。当然ながら、増幅段が多いほど不安定になりやすいのはお判りでしょう。
また、能動負荷の場合は、その影響が顕著になります。能動負荷の場合は、通常の構成だと2段目の利得が高くなる上に、その段の次に来る段が、たとえフォロアであっても、送り出しのインピーダンスが大きいために問題になりやすいわけです。特に入力キャパシタンスの大きいMOS-FETなどでは。
そういうアンプの出力段の帰還路を外して、「スピーカーの逆起電力の影響が云々・・・」等と言ってる方もいらっしゃるようですが、公正な評価とはとても言えません。
2.ゲイン配分
次に問題になるのが、ゲイン配分です。
この件については、ちゃんと書いてあるものを、不幸にして私はまだ見た事がありません。
これは、NFBがどうやって掛かっているのかを、実際の回路で良く考えてみる必要があります。図2に示す2段増幅器で、負帰還が掛かった状態でどういう動作をするのか考えてみましょう。
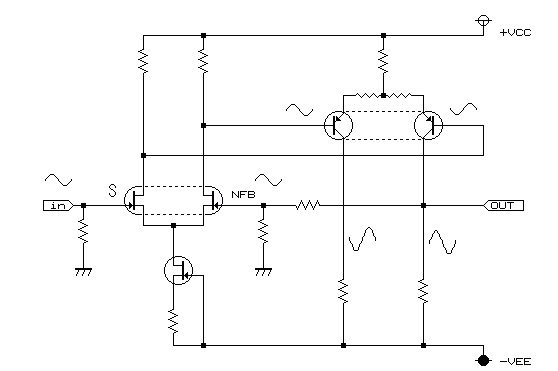 図2
負帰還増幅回路例
図2
負帰還増幅回路例
言うまでもありませんが、NFBを掛けたからといって各増幅段のゲインが減った訳じゃありません。
負帰還は魔法ではありませんから、例えばゲインAを持つ増幅段に対してkの振幅で入力があれば、その増幅段の出力振幅はA・kになります。これは負帰還の有無とは関係ありません。当たり前の話です。
では、どうして負帰還によってゲインが減るのかといえば、見かけ上、入力振幅が減るからです。これも当たり前ですね。だってそれ以外、方法が無いでしょ?
この様子を、図2の初段で考えてみましょう。
NFBの位相は、入力Sの位相と同じです。ですから、もしも負帰還側の入力振幅が、Sと全く同じであれば、出力には信号が現れません。勿論、出力がなければ負帰還もかからない訳で、結局、丁度都合が良いような振幅に落ち着こうとする訳です。
差動増幅はその振幅の差を増幅する事になります。
そこで、以下のような2つのゲイン配分について考えてみましょう。(利得は電圧で書いています。)
例えば、初段利得が10dBで2段目が40dBであるアンプに30dBのNFBを掛ければ、閉回路利得20dBになるのですから、当然2段目の入力振幅は-20dBという事になります。
逆に、初段が40dBで2段目が10dBのアンプに30dBの負帰還なら、2段目の入力振幅は+10dBです。
全く同様に、初段について考えると、どちらの場合も入力振幅は-30dBですね。総合利得が同じなのですから、当然です。
この例では、CMRRが十分に大と仮定して、Sが1[V]の時の負帰還側の振幅は、1-1/{10(30/20)}≒0.9684[V]
です。
ここで問題になるのが、ゲイン配分です。
即ち、2段目が高いゲインを持っている場合は、あたかも初段でものすごく利得を小さくしてから思いっきり大きくするかのように動作しますが、初段ゲインが高い場合には、見かけ上、初段で少し、2段目で少し増幅するかのように動作します。
つまり、負帰還によって、見かけ上は初段の利得が減ったような動作をしている訳ですから、初段の利得が大きく、2段目が小さい方が安定度は高い事になります。
誤解の無いように繰り返しますが、見かけ上はあたかもそれだけしか増幅しないような動作をしている、と言うことで、実際に増幅器の利得が変化した訳じゃありません。
初段の入力は、基本的には同相入力です。その振幅ないしは位相差分が出力に現れ、二つの出力は逆相です。
これに対し、2段目の入力には、基本的に同相分は存在しません。従って、入ってきた分がそのまま増幅されます。この為に、ゲイン配分に伴う安定度の変化が見られるのです。
(もしも初段のバランスがppm以下で揃っており、且つCMRRが負帰還量に対して無限大と見なせるほど大きければ、この限りではありません。逆に言えば、2段目のゲインが高いと、部品や構成、電源などの影響を受け易いと言う事です。)
また、この事から、初段に要求されるCMRR(同相成分除去比)は、2段目よりも重要であることも解るでしょう。
エンジニアなら当たり前と思っていて、アマチュアが知らない事も多々ありますが、私の見る所、これはその一つです。と言うのは、深いNFBを配したトランジスタアンプで、この逆の利得配分をしたケースを頻繁に見かけたのです。
(この一因は、有名なDCアンプの大センセーが、昔はそういう設計をしていたからじゃないかと思います。さすがに最近は、あまり見かけなくなりました。少しは技術が向上したんでしょう。でも、今頃ゲイン配分について大発見みたく雑誌に書かれると、笑いを通り越して呆れてしまいます。いったい、今まで何をやっとったんじゃ?)閑話休題。
真空管アンプは、普通は2段目のゲインを高くし難いので、案外とこういう問題は出ません。意外とこんな所が、自作派に真空管を是とする人が多い理由の一つなのかもしれませんね。NFB量も普通は浅いですし。つまり、失敗し難いんですな。
但し、真空管アンプでも、低域時定数を三つ以上持たせた時 −いわゆるミュラード型回路が該当する−
は、慎重にやらないと酷い目に遭います。よく考えずにやる人に限って、NFB悪者説を唱えたりするモンです。
NFBを巧く使いこなすには、それなりの技術が要りようである事がお判り頂けるかと思います。
これ以外にも、NFBの安定度に関わる問題は沢山あります。実装上の問題、アースの処理、定数の選び方、電源の安定性等々・・・
書き出したらキリが無さそうなので、この辺で止めておきますが、どんな問題にしろ、大切なのは「基本に立ち返る謙虚さ」ではないかと、‘かつ’は思っています。NFBの功罪による音の変化を唱えるのは、それからでも遅くありません。
3.帰還電圧波形と入力波形
あちこちで、この関係を誤解している例を見かけるので、追記しておきます。オーディオ雑誌なんかでも意味不明の事が書いてあったりするので、騙されない様にしましょうね(^^;)。
「帰還電圧と入力電圧とで生まれた結果が出力電圧であるから、そこに時間差があって然るべき」と考えるせいか、帰還に時間差があると思う人がいるみたいですが、単なる誤解です。
光速度での遅延はあるでしょうけど(^^;)、完全に無視できます。遅延時間と群遅延時間は全く別のモノです。負帰還は、群遅延特性を改善します。しかし、遅延時間の改善は出来ません(それが出来る装置はタイムマシンと言います)。
負帰還をかけたことで帯域が広がる、ということは、その広がった出力と入力との差を増幅しています。時間差とか、変な事を考えるとおかしくなります。全てはほぼ、同時に発生しているのですから。
ここで、誤解を避けるために、もう一度明言しておきます。
第一ポールが可聴帯域内に在ることは、最終的な帰還後の位相特性を含む伝達関数には、何の関係も在りません。
結局のところ、第二ポールとの関係で安定度が決まるので、述べたように第二ポールを上げられないのなら、第一ポールを思いっきり下げるか、利得を下げる(ゲイン補償と言います)わけです。( 2pole 補償やフィードフォワード補償を用いない限りは、ですが。)
IC-Op アンプの第一ポールは 100[Hz]以下に在るのが普通ですが、これをもって「だから Op アンプは音質が云々」なんて意味不明の雑誌記事を真に受けない様にしたいものです。
最終的な帰還後の特性では、帯域が広がっていますが、帯域を広げるために負帰還をかけている訳では無く、必要な帯域幅に於いてより優れた性能を得るために負帰還をかけます。
同様に、位相補償は、発振止めで しかたなく帯域を狭くしている訳では無いのです。
「フィードバックをかけていない増幅器に、フィードバックが追加された物として、フィードバック増幅器をモデル化する事は無益である」という、Rosenstart さんの言葉を噛みしめたいものです。