|
Forme. Fins and Swiming |
|
|
Forme. Fins and Swiming |
|
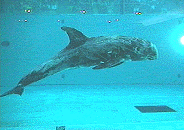 体型:どの種も水中生活に適した「紡錘型」をしています。1億4千万年前の海に居た「イクチオサウルス」という魚型のハ虫類は現世のイルカそっくり。同じ生態系で生活し続けると、その形態が似てしまうのは陸上の生き物と同じ道理。細かく分けると運動性能が高いスリムなタイプと、ポッテリタイプに分かれます。どの種類も必要以外普段はゆっくりと泳いでいます。 体型:どの種も水中生活に適した「紡錘型」をしています。1億4千万年前の海に居た「イクチオサウルス」という魚型のハ虫類は現世のイルカそっくり。同じ生態系で生活し続けると、その形態が似てしまうのは陸上の生き物と同じ道理。細かく分けると運動性能が高いスリムなタイプと、ポッテリタイプに分かれます。どの種類も必要以外普段はゆっくりと泳いでいます。一般にヒゲクジラは雌の方が大きく、歯クジラは雄の方が大きく成長する事が知られています。 (写真:ハナゴンドウ) |
 体色: 黒/灰/白を基本色とし、殆どのクジラ・イルカ類は腹側に何かしらの白い模様を持っている。ベルーガも白いとはいえ幼年期は体色がグレーである。反対に全身漆黒という鯨類は個人的に思い当たる節がない。マイルカと同亜種のハセイルカなどは横っ腹に黄色ないし燈色を帯びている。この鯨類の体色は生息場所が海面付近で有ることから「波/光/海水色」等に適応したカモフラージュ効果ではないかと考えられる。つまり自分が他者から見えにくい体模様程「狩りや防衛」に役立つ訳である。先に述べたベルーガの場合も海面に浮かぶ氷塊をイミテーションさせているのだろうか、ホッキョクグマ等も同じく白っぽい。基本的に体色・模様の原理は陸上の動物と変わらないのだ。 体色: 黒/灰/白を基本色とし、殆どのクジラ・イルカ類は腹側に何かしらの白い模様を持っている。ベルーガも白いとはいえ幼年期は体色がグレーである。反対に全身漆黒という鯨類は個人的に思い当たる節がない。マイルカと同亜種のハセイルカなどは横っ腹に黄色ないし燈色を帯びている。この鯨類の体色は生息場所が海面付近で有ることから「波/光/海水色」等に適応したカモフラージュ効果ではないかと考えられる。つまり自分が他者から見えにくい体模様程「狩りや防衛」に役立つ訳である。先に述べたベルーガの場合も海面に浮かぶ氷塊をイミテーションさせているのだろうか、ホッキョクグマ等も同じく白っぽい。基本的に体色・模様の原理は陸上の動物と変わらないのだ。 |
 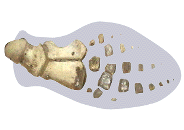 胸ビレ:主に方向転換や同種間でのスキンシップに使われており形状は様々。一部のクジラは胸ビレをヒレの形のへこみに格納し、水の抵抗を少なくしています。ザトウクジラに至っては「何でそんなにでかくて長いか」状態。いずれも人間同様「手首から先」の指の骨が入っています。
(右:オルカ左側手骨/国立科学博物館所蔵) 胸ビレ:主に方向転換や同種間でのスキンシップに使われており形状は様々。一部のクジラは胸ビレをヒレの形のへこみに格納し、水の抵抗を少なくしています。ザトウクジラに至っては「何でそんなにでかくて長いか」状態。いずれも人間同様「手首から先」の指の骨が入っています。
(右:オルカ左側手骨/国立科学博物館所蔵) |
 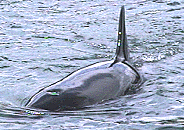 背鰭:泳ぐ際の横揺れ防止に役立っています。又、歯クジラ類の一部は性的二型により背鰭が大きく成長するモノもいます。環境により背鰭が消失した種や、ちょびっと背鰭?が着いているザトウクジラ系など様々。胸ビレと同様に運動性能が高い程、体に対してのヒレの面積が大きくなっている様です。 背鰭:泳ぐ際の横揺れ防止に役立っています。又、歯クジラ類の一部は性的二型により背鰭が大きく成長するモノもいます。環境により背鰭が消失した種や、ちょびっと背鰭?が着いているザトウクジラ系など様々。胸ビレと同様に運動性能が高い程、体に対してのヒレの面積が大きくなっている様です。○水族館で見られる「折れ曲がったシャチの背鰭」の理由として、水面から背鰭を出している時間が長く、重力の影響をモロに食らった結果という訳ですね。 |
  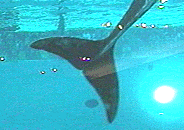 |
| ●シャチの尾鰭 ●ハンドウイルカの尾鰭 ●ハナゴンドウの尾鰭 |
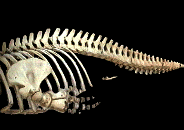 尾鰭:尾骨の後端に位置するヒレの中には骨は有りません。付け根の尾部はタテ方向に薄くなっています。尾骨下部には「V字骨」が有る。V字骨はカンガルーなど力の有る尾を持っている生物に良く見られる骨で、筋肉を付ける場所を提供すると共に、Vの凹みに太くて強い靭帯を通しています。余談ながら中生代の恐竜もこの「V字骨」を持っており、恐竜を調べていた頃から尻尾には当たり前の骨だと勘違いをしていた私は、鯨類を見てもピンとこなかったのです。もっと他の生物も勉強せにゃならないなと言い聞かされた骨でした。 尾鰭:尾骨の後端に位置するヒレの中には骨は有りません。付け根の尾部はタテ方向に薄くなっています。尾骨下部には「V字骨」が有る。V字骨はカンガルーなど力の有る尾を持っている生物に良く見られる骨で、筋肉を付ける場所を提供すると共に、Vの凹みに太くて強い靭帯を通しています。余談ながら中生代の恐竜もこの「V字骨」を持っており、恐竜を調べていた頃から尻尾には当たり前の骨だと勘違いをしていた私は、鯨類を見てもピンとこなかったのです。もっと他の生物も勉強せにゃならないなと言い聞かされた骨でした。※この骨・・V(ヴイ)と言うよりY(ワイ)に見えるんですけど。 ○尾ビレには他のヒレには見られない太い血管が通っており、水族館での血液検査はこの尾ビレの血管より採血をしています。又、この尾ビレでは「冷えた血液を含む静脈」と「暖かい血液の動脈」間での熱交換機能が備わっていて体温を調節していると考えられています。 ハワイ←→アラスカを往復するザトウクジラの胸ビレがでっけえ訳はもしかすると暑いハワイでの体温調節なのかもしれない。と断定は出来ないが、否定も出来ない程クジラや・イルカは多様なメカニズムを持っていて、全てが全て同じ特性を持っている訳ではないところがまたオモシロイです。 クジラ・イルカのドルフィンキックと言われる泳ぎ方は、陸上での四足歩行動物の走り方と同じ上下運動に良く似ていますね。彼らの祖先が陸上に住んで居たのですから無理に横に尾を振る様な進化は無かったのでしょう。あ、でもアザラシは横振りタイプだな・・。 遊泳中の尾ビレの振り幅はおおよそ「背鰭と、胸ビレの延長内」〜つまり、尾ビレは障害物への接触を避ける振り幅といったところでしょうか。もしくは脊椎の構造上、下方向に振りやすくなっている訳です。 魚は左右に振った尾から推進力を得ていますが、イルカに関しては下方向に振る尾ビレから推進力を発生させているようです。その他に急制動・急反転など尾ビレを巧みに使いこなしています。※イルカの運動力を観察するなら品川水族館をオススメします。アクリルガラス越しにイルカの水中ドリフトが観られて結構面白いですよ。 遊泳の他に意志表示にも尾ビレを使います。野生では気に入らない時は尾ビレで水面を叩いたりするようですが、水族館でも同じ事が言えます。又、胸ビレと同じ様にスキンシップや漂流物を引っかけて接触を楽しんだりもするようです。 (シャチ骨格写真:国立科学博物館所蔵) |
 トップスピード(シャチや舟に追われた時等)はシロナガスクジラで時速50キロ前後、カマイルカで時速55キロ、イワシクジラでは時速65キロとか〜なり速い。シャチでも時速64キロ、実際には瞬間的な計測でそのままずっと泳ぎ続ける事はできないでしょう。あくまでも参考一例であり、どのクジラ・イルカでも時速50キロ前後で泳ぐ事が出来ると考えています。 トップスピード(シャチや舟に追われた時等)はシロナガスクジラで時速50キロ前後、カマイルカで時速55キロ、イワシクジラでは時速65キロとか〜なり速い。シャチでも時速64キロ、実際には瞬間的な計測でそのままずっと泳ぎ続ける事はできないでしょう。あくまでも参考一例であり、どのクジラ・イルカでも時速50キロ前後で泳ぐ事が出来ると考えています。スピードと言えば、イルカが海面をすっ飛んで(飛び跳ねて)泳いでいる時・・・実を言うと水中で抵抗を受けて泳ぐより、海上に飛び出す方が抵抗が少なく「速く泳げる」為でもあります。えっと「ポーパシング」という呼び方で、ネズミイルカの泳法に例えられています(ポーパス=ネズミイルカ類)。 気になるのはデータや実験結果。彼らの体は流体力学を無視しているらしい。実際にイルカの模型やコンピュータで計算しても「そのスピードは出せない」というのが結論。だが、イルカやクジラは早く泳ぐ!速く泳げる理由の幾つかに、彼らの表皮からは酸化エチレン系の高分子化合物が分泌しており、まずこれが水の抵抗を減らしている理由の一つでしょう。(水族館のイルカ・クジラもよぉ〜く見ると光の加減で体が金色に光って見える角度があります。おそらくこいつでしょう)さらには遊泳中に表皮の一部が変形し水の流れを整流(乱流消し)しているという観察結果が出ています。マッコウに至っては体のデコボコに整流効果が有るのではないかという話も聞かれる。(ゴルフボールのディンプルみたいなもんかねぇ〜) |
|
 |
すっげえ泳力のネタでは飼育されていたミンククジラが直径3ミリの漁網をブッチ切って逃走する例が2〜3度有りました。これは回遊するヒゲクジラは特に尾ビレが大きく推進力もハンパでない事を物語っています。本気を出したクジラやイルカ達の泳ぐ速度や深度を計測してみたいものです。 |
| 歯クジラの殆どが潜水の達人?達クジラです。餌生物を採食する為と言って良いでしょう。又、潜って(採食して)いるのは夜間が多く、深い海の生物が浅い所まで上がって来るのが夜間でもあるのです。 潜水能力はマッコウクジラで3000m、ナガスクジラは水深200m、シャチの最大では1000mという記録が有り、海底ケーブルに絡んでいた死体から推測されました。バンドウイルカは300m位まで潜れるようです。(マッコウの3000mは胃の内容物から推測したもの)多くの資料を辿ると大抵のクジラ・イルカは平気で1000m近くまでは潜れる様ですが、実際にはそんなに深く潜る必要が無いので記録に残らないだけだと思うのですが・・。付け加えるとマッコウの表皮は他のクジラと比べてすっげえ固いそうですがこれもより深く潜る為の体の構造なのではないかと言われています。 クジラとは関係ない話なのですが、深い所で採食しているクジラの胃の内容物から深海性の「新種の生物」を発見する事も少なくないのです。 |
| 戻る | 次へ | |
|
|
Copyright(C)2000 Cetaceans Laboratry Aquaheart All rights reserved |