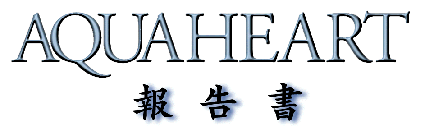 |
|
|
|
| 昨夜ゴキブリを捕獲した時「何故にゴキブリは滅ばないのか」と一時考えた。これを「軟骨魚類のサメ」を引き合いにし、さらに「鯨類」にまでこじつけてみたのだ。 ●ゴキブリやサメは太古のままの姿と体機能を有している。 ●数々の氷河期や大絶滅を乗り越え、現在も生態系地位は変わらない。 ●素晴らしく進化している訳でもない。至ってシンプルな構造。 数えあげればキリが無いが、彼らの共通点に「生態系的地位(ニッチ)に確実にはまっている」。これは周囲の生態系が変わってもそのニッチに割り込む「他の生物がいない」と考えている。いつの日にも自分の居場所が在る訳だが、それには彼らの「シンプルな構造」が物をいう。ゴキブリやサメの特徴を考えてみればそこそこ納得の行く答えが出てきそうだ。 何故「鯨類」までこじつけたと言うと、クジラやイルカもしかり・・・あそこまで海に融合した機能を持ってすれば大抵の氷河期・大絶滅を生き延び、種を存続し続けられるのではないかと考えた訳である。 (※人為的な捕獲による絶滅は含まない) 大昔、恐竜が栄えた理由の一つに大陸が一つで起伏が少なかった。そして滅んだ理由のひとつに大陸が分かれ、山脈等の造山運動が激しかった。つまり、大繁栄する際には「移動」が大きく貢献したが、その後の気候の変化を「移動」して逃れる事が出来なかったのではと考える。・・・・イルカは?そう、海は繋がっており、陸上に比べれば水温の変化も少ない。餌生物を追って、住みやすい海域まで泳いで行けば良いのである。 (※これに関して餌生物の状態や他種との競争等は考慮していない、簡単な思いつきである。) ・・・・・・・・簡単に答など出て来る筈はないのだが、動物を考えると面白い!キリがない!深い!最後には「地球の生物は全てリンクしている」といつもと同じ様にまとめてしまう。 |
| 横浜・八景島シーパラダイス「ドルフィン・フレンドシップ」8月4日(金)追加応募。 先日ムツゴロウさんこと畑氏がブラジルで「ライオンに指先をかじられてしまった」というニュースを見た。差程問題にならないのはあのお方だからこそなのである。弘法も筆の誤り・・・ムツゴロウさん気をつけられて下さいませ。余りファンをビックリさせないで欲しいです。 |
| 今年に入って水族館で気になる「お土産?」が目に付く。当ホームページで紹介している水族館、他各水族館では海洋哺乳類等のスケールモデルを販売し始めた。かの有名な自然再現型水族館モントレー監修のモデルは鯨類をはじめサメや両生類等、。シャチに関しては噴気孔の向きが逆であったりと多少の間違いも見られるが、揃えて見るのも一考である。今迄スケールモデルは自分で作っていたが、労力を考えるとついつい手が出てしまうのと、一時流行ったフルタのチョコエッグのせいでも有る。 ※イルカ・クジラのアクセサリーに惹かれる方には横浜クイーンズスクエア「at」にお奨めのお店が在る。お店の名前は「NOAHERT-CLUB」知る人ぞ知る名店。 |
| イルカの出産用撮影用備品購入:デジタルビデオテープ3本、ASA1600/400フィルム5本…経費でおちる訳ではない。(笑)イツモ使用の機材を紹介:DVはソニーPC-7、DVは暗い所でもキレイに撮影が可能、さらに持ち帰ってゆっくり動きを観察出来る。1眼カメラはミノルタα-7000というオートフォーカス第1号機。(骨董品)フォーカス速度は遅い!おまけにレリーズボタンがノートパソコンのトラックパッド方式で「皮膚」でなければならない・・・真冬手袋をしているとシャッターがキレないのである。 通常ホエールウオッチに使用するカメラレンズはF4.5/300mmの長玉を使用するのであるが、水族館使用が多い為28〜70mmのレンズを使用している。カメラ本体にはフラッシュ機能は無く、水族館での撮影には丁度良い。尚、デジタルカメラは動きの有る被写体は追いきれないので使用していない。 |
| 先週の「仔イルカ誕生レポート」を追跡取材&ページ更新。速報版では仔イルカの体長を小さく見積もってしまった。 最新版では江ノ島水族館・マリンランド北村正一飼育部長より詳細を伺う。 レポート記載以外にも興味有るお話しを頂戴したが、活字での表現方法を間違うとやっかいな事に成りかねず、必要最低限の記事にしてある。※この仔イルカの追跡取材は今年いっぱい続行。 7月初旬の出産に供え、携帯電話の着信音を上げて有る。出産開始の連絡は24時間受付中。 |
| 以前計画していた「鳥類飼育計画」は着実に進行しつつ有る・・・簡単な話、鳥を飼う訳なのである。 この所週末は厚木のペットショップに通っているのだが、目的以外の珍獣に目が奪われてしまう。 フェネックギツネなどは特徴有る種だけに一目で判るが、白黒のブチイヌ?を触ってて顔を見たら名の知れないキツネだったりする。ケージの品定めをしていると足元で「ガリガリ」してるヤツが居る、別に痛く無いから気にしないでいると、ミーアキャットが靴紐を解いていた。店内を模索中何かに袖が引っかかったと思いきや、リスザルが袖を掴んでいる。実に楽しい・・・いや不思議なショップである。 お目当てはというと「白の文鳥」と「ルチノーのオカメ」。イルカやクジラの事は少々判っているつもりだが、鳥に関しては全くと言って良い程判らないのである。 |
| 一週間ぶりの報告書と仔イルカ誕生のページを更新。画像はSONYデジタルハンディカムより取り込んだ荒い画像で、近日中にスチル写真を再アップ予定。ちなみに仔イルカの撮影は非常に難しい!動きが機敏なのと、水面上に出る時間が成体よりも遥かに短いのである。確かに…以前生後2ヶ月のイルカの撮影の時も難しかった覚えが有る。次回は出産を立ち会うつもりであるが、相当苦労するであろうか。 某イルカ関係の掲示板より咲来小学校3、4年生の子供達が「いるかのひみつ」を研究中との事。掲示板の書き込みと共に、小学校宛に電子メールを送る。彼らの探求心に、一つでも役に立てる事が出来ればとても嬉しい限り。 |
| 横浜・八景島シーパラダイス「ドルフィン・フレンドシップ」の参加が決まった。参加は7月8日(土曜日)企画初日である。昨年は「Salty
Dolphin」というレポートを作ったが、今年は「Salty Dolphin.whale&Porpoise」というレポートになるだろう。(訳:イルカ、クジラ&ネズミイルカ海水カクテル)。 ・・・・楽しみだ。 |
| 2週間ごぶさたしていた江の島水族館・マリンランド行き。予定されていたイルカの出産が6月7日に終わっている事を聞き、何とか本日見に来る事が出来た。午前9時30分〜12時まで観察。生まれて11日目のイルカにしてはやや小さく思えるが、寺沢獣医師によれば許容範囲内であるとの事。プール脇の防護用柵(仔イルカ用)に苦労が伺える。又、カマイルカの泳ぐクリスタルプールでは、昨年に引き続き大学生の研究が行われている。この日のショーではメスのバンドウイルカ「シャドウ」が全般参加している。 以前にも報告していたが、「イルカの区別」がほぼ完璧になっていたのに気付く。いつの間にか遠くからイルカの区別が付くようになっていた自分に多少驚いてしまった。 |
| 一週間ぶりの報告書である。 本日は国立科学博物館・新宿分館へ足を運ぶ。以前より話しの有った科博鯨類のページ作成の件であるが、諸々の事情により長引きそうな気配。話がまとまればより充実したページにしたいモノである。 又、科博の図書室にて「鯨研通信」「日本動物園・水族館雑誌(動水誌)」他を閲覧。 |